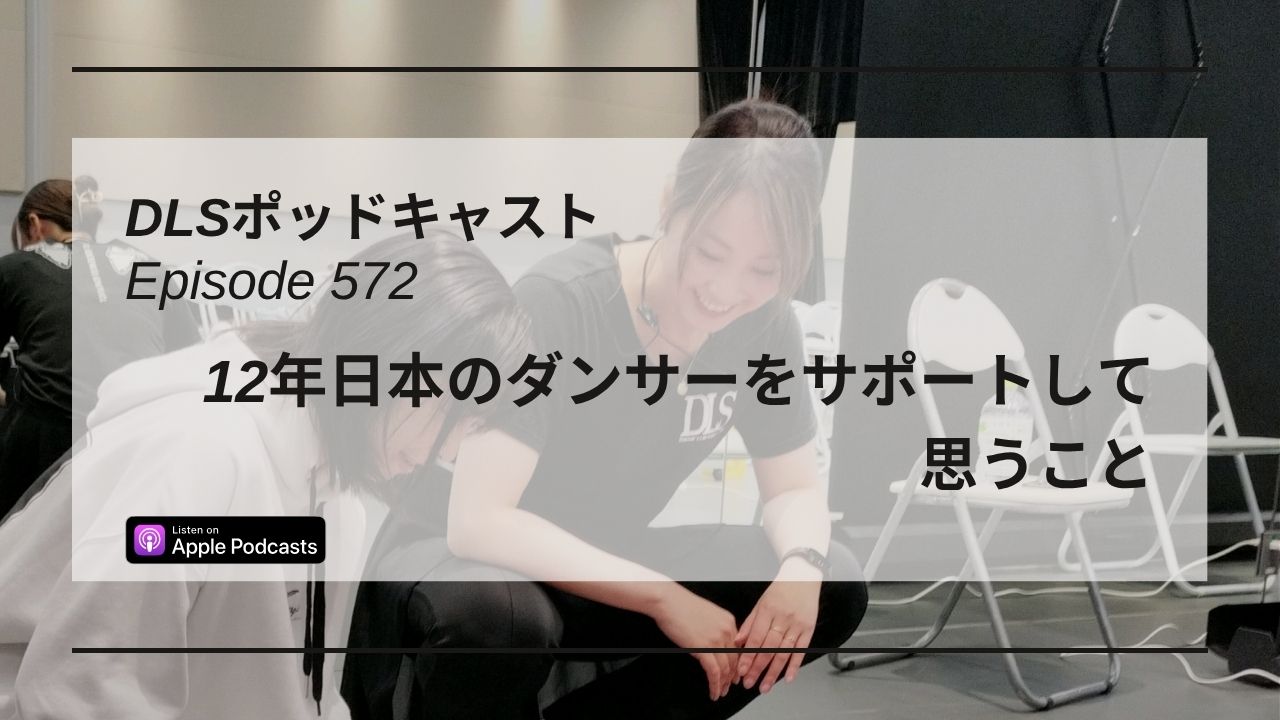日本のバレエ界を外から見てきて12年。
元海外バレエ学校の治療家兼講師を務めた佐藤愛が思う、
日本のバレエダンサー特有のポイントをお話したポッドキャスト。
流行りに飛びつく前に、「みんながやってるから」という前に一度聞いてみてください。
Transcript
2014年の本日、8月1日にDLSポッドキャストを始めた佐藤愛です。
当時は、ポッドキャストと言っても知らない人がほとんどで、
「ネットラジオです」と説明していたんですが、今はポッドキャストで通じるよね?
スマホ、特にiphoneの普及で、
すでにデフォルトで入っているポッドキャストアプリのおかげかもしれませんし、
コロナのとき、ラジオ局に行かなくてもポッドキャストができるじゃん!
という芸能人が多かったからかもしれません。
海外で普及して、数年たったら日本にやってくるという
いつも通りの流れの可能性もあります。
どんな理由にしても、DLSにとって、ポッドキャストは
世界各国にいる日本人ダンサー、バレエ関係者たちへ、
無料で手軽に情報提供する場所の1つとして
毎週欠かさずお送りしてきました。
今年で11年目になり、年季が入ってきたDLSポッドキャスト、
お誕生日スペシャルの本日は、12年間DLSを通じて、
日本のダンサーたちをサポートしてきて思うことを3つ挙げてみたいと思います。
最初は、5つの予定だったのですが、
あまりにもエピソードが長くなってしまったので3つに絞りました。
スタートする前に、ディスクレイマー、免責。
これは私が勝手に感じていることであり、エビデンスベースではありません。
日本人ダンサー全員がOOである、と言っているわけではありません。
日本人だからダメ、とかダメだしでもなく、
「こういう文化なんだなー」と思って外から覗いている、
という感じだと思って聞いてください。
ま、こんなことを言わなくても、
ポッドキャストリスナーさんならわかっているとは思うけど!
では行きましょう。
日本のダンサーたちをサポートしてきて思うこと:流行りに流されやすい
10年以上日本のダンサーたちを見つつ、
オーストラリアのバレエ学校やバレエ団、
英語圏の情報を読んでいて思うことナンバー1は、
日本のダンサーたち、保護者、先生たちは、流行りに流されやすい。
そういう私も、日本にいるときはそうでした。
先輩たちが履いているからカッコいいと思ったニットパンツ、
講習会に行った先で見たから買ったサウナパンツ。
ローザンヌバレエコンクールのやっていた講習会先で売っていたループになっているバンド。
使い方もよく分からなかった癖に、ローザンヌ決戦で使っている人の写真、
今思えばプロモーション用にステージして撮った写真、を見て購入しました。
オーストラリアに留学してきたときも持ってきました。
この赤と黒のループになっているバンド、分かる人いるかなー
同世代の先生たちだったら知ってるかな。
これね、今エビデンスベースで、エクササイズや解剖学を指導している側として、
危険極まりない道具だって知っているんですが、時すでに遅し。
日本ダンサーと仕事をするようになってから見た流行りは
シャカシャカ音がなる、ブーティーって日本でも言う?
ウォームアップブーツみたいなもの。
あと、花柄のレオタードの多いこと!
最近はかぎ編みのショールのようなものを、
腰に巻くのが流行っているように見えます。
どれも悪いって言っているわけではありません。
ただ、みんな同じような恰好をしているなぁって思います。
さっきお話したように、私も子供のころやっていたので、
子供たちが先輩や、憧れダンサーの真似をする気持ちはよくわかります。
これを着れば、やれば、身に着ければ、食べれば、この人みたいになれる!
みたいな暗示があるのでしょう。
バレエカンパニー内で流行るというのもよくわかります。
同じような環境で、たぶん同じ学校から来た、同じくらいの年齢の子たちが、
外の世界に触れるよりも、身内と一緒にレッスンしている時間が長い仕事場にいるので、
お揃いにしよう!みたいなのが多いのかもしれません。
でも、日本独特だなと感じるのは、
そのような流行りを追っかける行動を、
- 大人(先生や保護者)がやること
- そして大人(先生や保護者)が子供に勧めること
の2点です。
大人バレエダンサーが流行りに乗っている場合、ちょっと意味が異なるので
ここでいう大人とは先生や保護者のことだと思ってください。
保護者が可愛いから、と言って買ってくるバレエ用品を小学生が使う。
くらいのレベルならまだいいかもしれませんが、
保護者がOOダンサーがネットでこういうダイエットしてたから!
みたいな感じで真似してしまうと
ボディイメージなど、多くの問題を作ってしまいます。
何よりも、専門家ではない人がやっていることをネットで見て、
専門家ではない自分が勝手にまねて、
子供の将来に影響する行動、健康や安全に影響することをする。
これは親として怖くないのかな?と思ってしまいます。
プロダンサーだったとしても、結局は、あなたの子供のことを知らない赤の他人でしょう?
でも、このような保護者がやるべきではないことについては、
6月のポッドキャストでお話したので今日は割愛しますね。
生徒たちが、憧れの先生を真似するというベクトルではなく、
先生が、流行っているからうちのスタジオでもやろう!
みたいな感じで持ってくるというと、
それは、流行りの真似ではなく指導になります。
レオタードくらいなら問題ないかもしれませんが、
それが、流行りのストレッチ、流行りのダイエット、
テレビで見た”健康情報”だと困るのです。
知らないことは、指導できないから。
この言葉は、今年で12年になるDLSで何度も言ってきましたが、
大事なのでもう一度。
ガクリヤードが何かわからなかったら、指導できないでしょう?
たとえ、くるみ割り人形のように、みんなが知っている古典バレエで、
金平糖の精の音楽は、バレエをやっていない人でも知っていて、
もちろん、何度もYouTubeで見たことがある振付だったとしても。
指導者が、正しくこの動きを知らなかったら
生徒に正しく指導することはできないのです。
これが「知らないことは指導できない」。
「こんな感じ」と見せることができたとしても、
それは指導ではないでしょう。
日本のダンサーたちをサポートしてきて思うこと:理論的に考えるのが苦手
流行りに乗るのが好き。
という1つ目のポイントの続きのようになるのですが、
日本のダンサーたちをサポートしてきて思うこと、
その2は「理論的に考えるのが苦手」という点。
- OOさんがやってたから
- XXで取り上げられていたから
などは、話のきっかけ、興味を抱くポイントとしては当たり前だと思うんですね。
そうじゃないと、自分が知っていること「だけ」で世界が確立してしまうため、
非常に狭い視野で生きることになってしまいます。
だけど、その後に「興味があるから調べてみよう」に行かず
あたかも事実のようにほかの人、
さっきの例では子供たち、生徒たち、に伝える様子が見られます。
そして、「どうして、そうするのですか?」と聞くと答えることができない。
大体の場合、出典元さえ忘れてしまっているため、ファクトチェックもできないし、
何歳の人、どんなレベルの人、どんなバックグラウンドの人がやっているのか?
という重要な情報がなく、
who, why, whenをすっ飛ばして、多くの場合、howもすっ飛ばして、
「what」だけが残る気がするのね。
例としては、
骨盤矯正、筋膜リリース、肩甲骨はがし…など
バレエとは関係ないところからスタートした言葉を
あたかも解剖学用語のようにレッスンで使っている様子。
1つ1つの言葉や行動が、絶対に間違いだと言っているわけではないです。
必要な人もいるでしょう。
例えば、出産後、ホルモンやお産の状況によって確かに、
仙腸関節が左右非対称にかみ合っている可能性はあるかもしれません。
しかも、腹直筋の乖離があるため、運動制限があり、寝不足も続く最初の6か月は、
体への負担を減らし、傷口が修復しやすいように、
骨盤矯正ベルトが必要な方もいらっしゃるでしょう。
その結果、おしりが小さくなったとか、痩せた!とかいう人たちがいますが、
それは妊娠中は出産に向けて骨盤は広がり、
赤ちゃんだけでなく、胎盤などエクストラの臓器も運ぶのだから、
骨盤矯正ベルトの有無に関係なく、サイズが変わって当たり前なのですが、
やっぱり理論的に考えるのではなく、
ガラスの靴や魔法の杖と同じレベルで、
骨盤矯正ベルトがスペシャルアイテムに見えてしまうようです。
手術後、瘢痕組織がスムーズになるように、
マッサージやリリースを行う人もいるかもしれません。
オフィスでパソコン業務、運動不足、ちょっと四十肩のきらいもある人だったら、
肩甲骨周りを大きく動かす理由がよくわかります。
でも、
- who、誰が
- why、どうして
- when、どのタイミングで
- how、どうやって行うか
が分からなず
- what、SNSで見た行動
をやっていても、意味がないだけでなく、ケガのリスクがアップすることも。
- ちゃんと調べてみよう
- 複数の出典元を探してみよう
- ケガしているのなら、治療家の先生やリハビリの先生に聞いてからやるか、やらないかを選ぼう
- バレエの話だったら、先生に聞いてからにしよう
と考えられるといいのになぁって思います。
もしかしたら、これができない理由の1つに
学校教育で質問をする子は静かにしなさい、と言われるとか、
先生に好かれたいんでしょ、みたいにクラスメイトに言われるから、
というのがあるのかもしれないなぁ、とこのポッドキャストを作りながら思いました。
- 特に先生と呼ばれる上の立場の人たちへ、質問をしてはいけない
- 先生、先輩に言われたら従う
- 目立たないように、周りと同じ行動をとる
これらが、学校や会社の「良い生徒」「使いやすい部下」を作るのだとしたら、
1つ目の、大人でも流行りを追うこと
2つ目の、理論的に考えない
というのが褒められる環境にあるのかもしれません。
まぁ、そうはいっても21世紀、スマホ時代の私たちですから、
先生に聞かなくても、理論的に考える力があれば、
ツールは無料で、手のひらに入っているはずなんですけどね。
日本のダンサーたちをサポートしてきて思うこと:プロダンサー向きな性格
日本はダメなんだから!と思う前に、
日本のダンサーたちをサポートしてきて思うこと、最後のポイントを聞いてください。
私は日本のダンサーたちは「プロダンサー向きな性格」だと思っています。
実は、バレエ向きの子たちとは、
さっきあげた「良い生徒」「使いやすい部下」の気質があると言われています。
いい意味でも、悪い意味でも。
- 先生に言われたことを、ちゃんと続けることができる
- 注意されたことを覚えている
- ほかの子が注意されたことは、自分のことのように聞いておく
というのは、上達するために大切なポイントです。
古典バレエのような昔からの文化がある場合、
- どうしてそうやるんですか?
- その表現はおかしくないですか?
など聞かれても、答えは
- 昔からこうやってきたから
となります。
だから、自分で考えず、言われたことを繰り返すロボットの方が
先生も、振付家も楽なんでしょう。
なので日本人生徒は、バレエ学校で好かれやすいのかもしれません。
もちろん、周りと揃えるというのが、古典バレエの美なわけだから、
自己を前に押さず、周りと同調する力が必要だという見方も出来るかもしれませんよね。
バレエ学校で働いていたとき、国籍に関係なく
言われたことができるダンサーは上達していました。
良い先生がついていれば、良い指導内容を真似していれば上達して当たり前ですし、
治療家目線では、言われたとおりにリハビリプログラムをこなしてくれると、
一番スムーズにケガから復帰できるので、私も助かりました。
トウシューズは3週間目から、と言ったのに
調子が良かったし、先生にリハーサル出れるよね?と言われたから踊っちゃいました
と言われると、正直腹が立ったものです。
今お話したように、国籍と関係ないのかもしれませんが、
小さい時から、言われたことをやる。
という習慣がついている子たちの方が、バレエ学校でも楽だとしたら、
そういう習慣が学校文化で学べる環境にいる可能性が高い日本人は、
居心地の良い環境になりやすいのかもしれません。
もちろん、バレエが頑固爺さんで、何世紀も前のバレエのままだ!
と言っているわけではありませんよ。
私は、バレエは進化し続ける伝統芸術だと思っています。
古典という箱の中で、どれだけ自分らしく踊れるか?を深く考え、
自分の領域を作って踊っているダンサーたちもいるし、
古典という箱と時代背景を理解したうえで、現在のモラルに則り、
民族的ステレオタイプの振付、名称はやらない、
と判断するカンパニーも増えてきました。
古典作品を、別の角度から見た、
マシュー・ボーンのスワンレイクや、マッツ・エック版のジゼルなどもありますよね。
不思議の国のアリスのように、今後様々なカンパニーで踊られるだろうと思われる、
古典テクニックと、タップなどほかのジャンルのダンスや、
プロジェクターなどの視覚的要素などを取り入れた作品も、
今後もっと出てくることでしょう。
観客としては嬉しいですよね。
私も、同じお金をだすなら新しい解釈が見たいし、
どうせ見るなら、楽しいものを見たいもの!
進化するバレエへ、進化するダンサーへ
だからこそ、ダンサーも進化続けなければいけないと思います。
ただ、ダンサーが進化するためには、指導者が進化しなければいけないでしょう。
- 流行ってるから
- 昔からこうやってきたから
- OOバレエ学校でやっているみたいだから
みたいな指導では、小さな視野の、時代遅れなダンサーしか育たないですよね。
骨盤が広がってるから、バレエ向きじゃない。なんて言ってしまう先生がいたら
その人の判断基準はバランシンが指導していた戦後直後のレベルになっています。
戦後恐慌(せんごきょうこう)の食事が十分にとれない時代で、
その上ベビーバレリーナ、と言われるような細く、子供体型のダンサーが好きだった…
彼の作品は素晴らしいけれど、指導者としての彼、人間としての彼は
良い人というカテゴリには入らないと思います。
私だったら、生徒を預けたくないね。
細く、ひ弱な女の子の方が美しい。
これは1841年のジゼル初演から184年も経った
2025年の日本でも、まだ言われているんじゃないでしょうか。
日本の流行りの1つ、色素薄い系も、
多くの人が海外は進んでいると言うけど、それはアングロサクソン系の国だけを指して、
アジア圏は毛嫌いする傾向があるバックグラウンドを考えると、
白人至上主義の1つから来ているのではないか?と疑っていますが。
この考えが、
- 筋肉がつくのが怖くてエクササイズできない
- ストレッチ、つまり筋肉を使うのではなく、伸ばしていればOK
- ケガしていても、痛みの中で踊るのが努力であり、バレエを愛してる証拠
という考え方の根本にあるのかもしれません。
その考えが助長される場として、馬鹿みたいに多いバレエコンクール。
バレエ雑誌には絶対に含まれる特集として、痩せることにフォーカスした食事や情報。
バレエでなくても、太っていたら笑われる役として、芸能人も扱われる。
残念ながら、こういった文化がある中で
- 流行りに乗る
- 理論的に考えない
という癖がついていると、時代遅れのダンサーになること確実ですし、
心と体の健康面を考えると、長く踊り続けられないでしょうね。
DLSも12歳になりました。
スタートした時の流行りは、今は見られませんし、
バレエ解剖学やエクササイズが広がってきた感じはあります。
ですが、ケガしても踊り続ける”努力”、”バレエ”体型、
解剖学を無視したストレッチへの考え方は変わらず、存在しています。
どう考えたら、それが正解になるの?
と思えるような情報が、ネットで流行るし、
今からはAIで作られた嘘情報も気にしなければいけません。
今年最初のポッドキャストは、バレエの歴史と踊りのレベルをお話しましたが、
バレエ自体、成長しています。
テクニックも、ダンサーに求められるレベルも、振付の幅も。
だからこそ、ダンサーも先生も、バレエ関係者も、そして私も。
時代に合わせて、進化していかなければいけないんじゃないかな?
- 日本の素晴らしいところ
- 日本人の誇るべき文化
を大切にしつつ
100年前、50年前と同じことをしていたら、
足りないという事実を理解すべきじゃないかな?
そんなことを考えて、お誕生日ポッドキャストを終わりにしたいと思います。
12年、応援してくださってどうもありがとうございました。
これからも、DLSが皆さんのバレエ生活を、
プロの現場から応援できる場所になりますように、
(この言葉、覚えてる?DLS初期のスローガンでしたよね)
生徒の安全と将来の健康を第一に考えるレッスンが当たり前になりますように。
進化し続けたいと思います。
Happy Dancing!