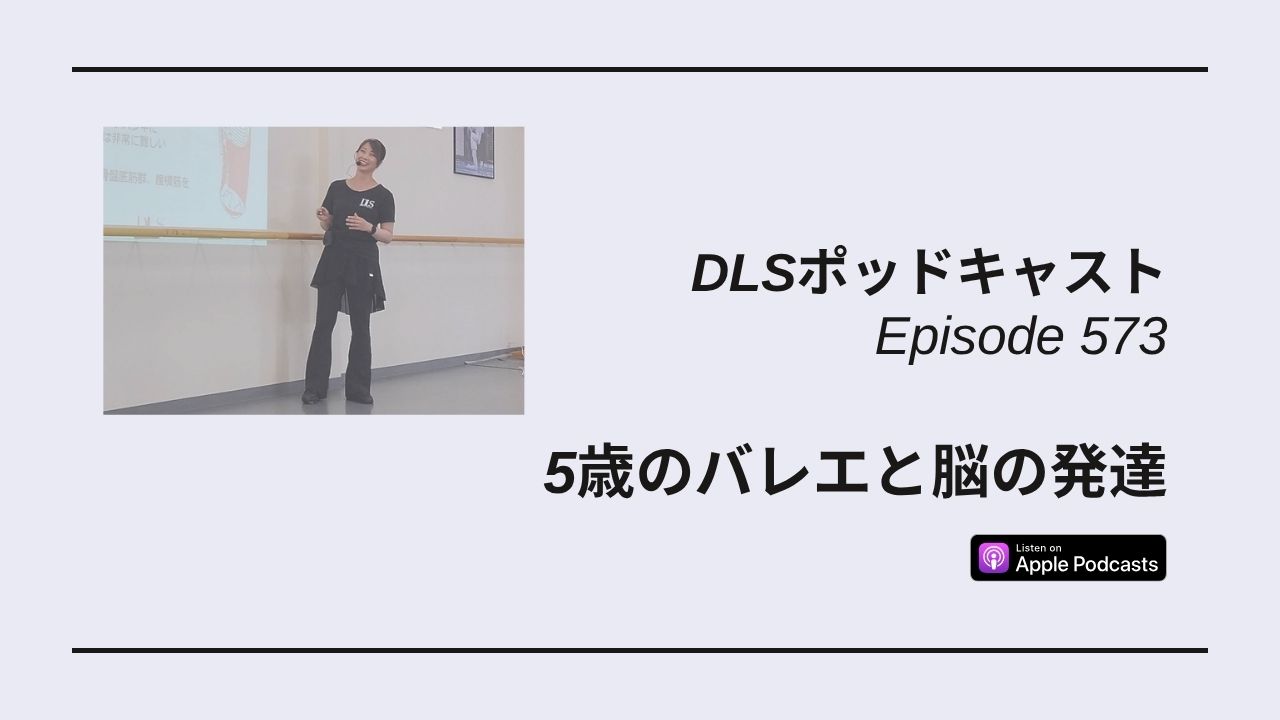日本のバレエスタジオでは幼稚園生の生徒さんが多いですよね。
ゆっくり基礎レッスンをすればいいんでしょう?
と思っている先生はもちろん、バレエを習わせている保護者にも聞いてほしい、
5歳児の脳の発達から考えたバレエレッスンについてお話しました。
Transcript
先月のビーチホリディで、5歳の姪っ子と2日過ごしたら、すごく疲れた佐藤愛です。
元々子供は苦手なんだけど、友達の家族が増えてからは、
皆さんご存じの、毎年恒例のフレンドケーションで
20人越えの子供たちと時間を過ごすことも多くなったのですが、
今回は結構パンチが大きかったんですよ。
彼女ね、いい子なんです。
よく喋るし、幼稚園で習ったアボリジニのダンスをずっと踊っていてバレエも習っている子なのね。
走り回っているわけでもないし、目を離したら、犬を引っ張ってるような赤ちゃんでもないし。
では、なんでこんなに疲れたのか。
少し時間が経ってから考えた推理は、会話が成り立たないからだと思いました。
去年同じ時期に会った時と比べて、語彙力がアップしているのを感じました。
びっくりするほど難しい単語を知っているし、架空の話は、架空の話、と理解できているみたいなんです。
だから「パン屋さんにみんなで住もう」と言い出した時に、「どんなパンを売るの?」と聞いたら
「パン屋さんに住むけど、パン屋さんじゃない。」と言うんですね。
その後、パン屋さんについて色々聞いていたら、「ごっこ遊びなんだから、本当にはしない」とぴしゃっと言われました。
じゃ、なんでパン屋さんに住むのか?
答えは、ただ単純に彼女が毎日パンを食べたいからだと、後から気づきました。
架空の話と、現実の区別はつくけれど、パン屋さんに住んでも、食べてるだけで作らなければ、
パンはなくなってしまうという事実には気づかなかったようです。
そりゃそーだ。
彼女の中での「事実」は、100%、間違いなく、パン屋さんに行ったらパンがあるんだから
作るという考えに至らなかったのでしょう。
こんな感じで、話が成り立たない生活を2日送っていたら、
聞くのも大変だし、話すのも大変。
しかも、話が通じないと機嫌が悪くなる。
これが大変だったんだーと気づきました。
ピアジェの認知発達理論
スイスの発達心理学者、ジャン・ピアジェ(Jean Piaget)は、
子どもが思考力を発達させていく過程を4つの段階に分けて特徴をまとめています。
- 0~2歳は感覚運動期
- 2~7歳は前操作期
- 7~11歳は具体的操作期
- 12歳以降は形式的操作期
と呼ぶそうです。
姪っ子が当てはまるのは前操作期。
心理士の記事によると、このグループは
- 象徴的思考(symbolic thinking)を始め、言葉や絵を使って物を表すようになる
- 言語能力や思考力は向上するが、まだ論理的思考は苦手
- 他者の視点に立つのが難しい(自己中心性)
- 保存の概念(constancy)を理解できない
そうです。
道理で疲れるわけですよ。
単語は増えるし、会話はできるし、いろいろと説明したりしてくるけれど、
理論的ではないので、思考の流れについていくのが大変でした。
しかも、自己中心的な行動が多い。
でもこれは、彼女が自己中なのではなくて、
まだ他人を考えられるだけの脳みそが育っていないということ。
実際にこんなエピソードがあったのね。
夕飯と、アイスクリームを食べにビーチに行きました。
出かける前は、バニラのアイスが食べたいと言っていたのだけど、
到着したら、レインボーのアイスクリームが食べたい、に変わっていて。
バニラは探しやすいけど、レインボーはとっても大変。
ほかの味は?とみてみたけれど、レインボーの一点張り。
それがあるお店は、ちょっと離れていて、しかも犬たちは一緒に行けない場所でした。
彼女の両親が、
- 犬たちが行けないから無理だよ
- ほかのアイスにしようよ
と伝えても涙しているだけ。
結局お父さんが、彼女を連れてアイスを買いに行ってくれました。
それがおいしかったのかと思ったら、
ビーチで楽しかったのは、夕飯に食べたフィッシュ&チップスだったらしく。
レインボーのアイスクリームじゃないの?と聞いたところ、
もう覚えていませんでした。
あれだけ、みんなを止めて地団駄踏んでたのに!
5歳の子供の理解力
別にポッドキャストを聞いてくださっている皆さんは、
愛さんが5歳の子供のアイスクリーム事件で疲れた話、は興味がないことでしょう。
でもね、5歳ってバレエスタジオにたくさんいる年齢じゃないですか。
日本の場合、3歳くらいからバレエを始めているスタジオも多いですし、
5,6歳ではコンクールに出ている子たちもいるようです。
昔、DLSでバイトをしてくれていた、元バレエ学校の卒業生の一人は、
働いているスタジオで、人数の関係か5歳の子も小学生クラスに入っていて、
小学校高学年たちと一緒にシソンヌしている、と言っていまして。
確かに同じ学校に通っているかもしれないし、友達同士かもしれないけれど、
脳の発達段階を考えると、同じ理解力なわけではないんですよね。
たとえ、いっぱい喋っていたとしても。
ジェローム・プラドの論理的思考の発達を心理学的・神経科学的視点から分析した研究によると
このくらいの年齢では、具体的な情報を与えると、ある程度の理論的推理ができるそうです。
Aということは、Bだ、と分かるということ。
例えば、腕をすりむいたら、ケガをしていることになる。
ただ、AということはBだ。
つまりBということはAだ!と理解しちゃうらしく、ケガをするということは、腕をすりむくことだ!とつながってしまい、
ケガの原因がそれ以外だと考えつかないんですって。
でも、こういう大人もいますよね。
森下洋子さんは3歳からバレエを始めた。
3歳からバレエを始めたら、森下洋子さんのようになれる!みたいな考え方。
これは、5,6歳児の脳みそ状況ですってよ。
5歳の子供がバレエをする場合
では、5歳の子供たちがバレエをする場合、
親や先生は何に気を付けたらよいでしょうか?
今日は、ピアジェの認知発達理論と、プラドの研究から、
スタジオでできることに合わせてみましょうか。
象徴的思考、具体的な情報が必要なので、先生のお手本が大切
でもそれは、先生がプロダンサーだったらOKというわけではありません。
だって、その子たちのレベルで、テクニックをやっているわけがないから。
完璧なターンアウト、甲の出た足が必要なのではなく、
彼らのレベルで必要な動き、例えばブラバーの手の形とか、
スキップで斜めに進む、音楽に合わせて手を叩ける、とかのレベルね。
間違っている、できない=分かっていないわけじゃない
できない理由は、ただコーディネーション力の問題かもしれませんし、
慣れていないだけかもしれません。
その子に、才能がないわけじゃないんです。
その子たちの年齢だったら、新しいことがたくさん必要なのではなく、
同じ動きを何度も繰り返し、神経回路を作ったり、理解を深めたりするのが大切。
子供たちは、お気に入りの音楽があったらずーっと歌ってるし、
同じ映画を何度も見たりするでしょう?
姪っ子が、アボリジニの踊りを毎晩繰り返しているのと同じで。
先生は飽きてしまうかもしれませんし、
保護者は、先週もやったじゃない!と思うかもしれないけれど、
びっくりするほどゆっくりペースのレッスンが、年齢に合っているレッスンとなります。
抽象的な言葉ではなく、具体的に伝える
プラドの論文にもあるように、
「幼い子どもは具体的な文脈がある場合のみ推論ができる」そうで、
彼らはまだ、抽象的な言葉や雰囲気、ニュアンスを理解できません。
引き上げて!ターンアウトして、はよくわからないんです。
その代わり、
- おへそをバーの方向へ、でアンファセの理解
- スカートをつかんで、バレエの指の形の練習
などはできるはずです。
つまり、先生たちが徹底して、具体的に、クリアに注意を理解していなければ、
こんな感じ、で通じる学生ダンサーたちよりも難しい指導になるかもしれません。
鏡は必要ないかもしれない
まだ他人への理解ができず、
自己中心的な考え方の脳の発達をしている年齢層なので、
鏡を見ながら、自分の動きを理解することは不可能なんじゃないか、と思います。
過去にブログにしましたけど、
鏡を見てレッスンするのは、ある程度のレベルになっても難しい。
しかも管理栄養士、フミさん曰く
女の子は3歳くらいから他の子と自分の体形を比べ始めると言っていますから、
ポジティブなボディイメージのためにも、鏡を見ないのは大切かもしれませんね。
先生たちも、鏡を見てレッスンをしているとき、
生徒ではなく自分の体を見ていることが多いですから、
良い指導のためにも気にしたいポイントです。
チャレンジすることが大事
ピアジェは「子どもは小さな科学者のように試行錯誤しながら世界を理解する」と言っています。
プラドも、「論理的思考の発達は多くの失敗と繰り返しの中で形成される」と言っています。
そのため、この年齢の子たちに必要なレッスンは
正しく振付を覚えること「だけ」、間違えないこと「だけ」ではなく、
安全な範囲で、試行錯誤できるようなこと、想像力を使えることなどを取り入れたいところです。
そして、チャレンジしてみたことをほめてあげる必要があります。
例えば、シャイな子だったけど、インプロにチャレンジしたとか、
想像力を働かせて表現していたとか
いつもと違う子とペアになったとか。
5歳のバレエコンクール
この子達の年齢に、コンクールレッスンは必要ないというのも理解してください。
早い段階で競争の世界に入れると、
- 内発的な動機、楽しみを失うということ
- 自己肯定感の低下につながること
- 成功しないと価値がないという考え方を作ってしまう
というのは、研究等で分かっています。
今日見てみた2つの研究から、
AということはBだと理解するけど、
BということはAだ、と理解してしまう
と話したじゃない?
つまりね、コンクールで賞を取ったらすごい、と理解すると
- すごいのはコンクールで賞をとることだ
- コンクールで賞をとれないのはすごくないんだ
と理解してしまう恐れがあるということなんです。
彼らはそれを口にしないかもしれないけれど、
このような考え方は、大人になった時にも影響してしまいます。
いつもと違うことは刺激的です。
想像力が豊かな子たちにとって、衣装は楽しいことでしょう。
舞台の後に、お花をもらったり、ほめてもらえるのは嬉しい体験です。
だから発表会がダメ、と言っているわけではないですが、
子供とは、大人のミニチュア版ではないんですよ。
成長期ダンサーの体は、大人のミニチュア版ではないと説明したことがありますが、
今回みたいに幼稚園、小学生の脳みその発達面からも、大人のミニチュア版ではないんです。
だからこそ、大人が焦らないこと。
それが5歳のバレエをエビデンスベースで考えたとき、一番大切な学びだと思います。
疲れると思うけどさ!
DLSには「保護者が知っておきたい成長期の体」オンデマンドセミナーがあります。
5歳児には関係ないですが、
彼らが成長していく前に知っておきたい事がつまったクラスになっているので、
保護者の方はチェックしてくださいね。
DLSサイトで「保護者が知っておきたい成長期の体」を検索してくださってもいいですし、
インスタでDMしてくださったら、リンクをお送りいたします。
ではまた来週、5歳児とバレエについてお話していきましょう。
Happy Dancing!