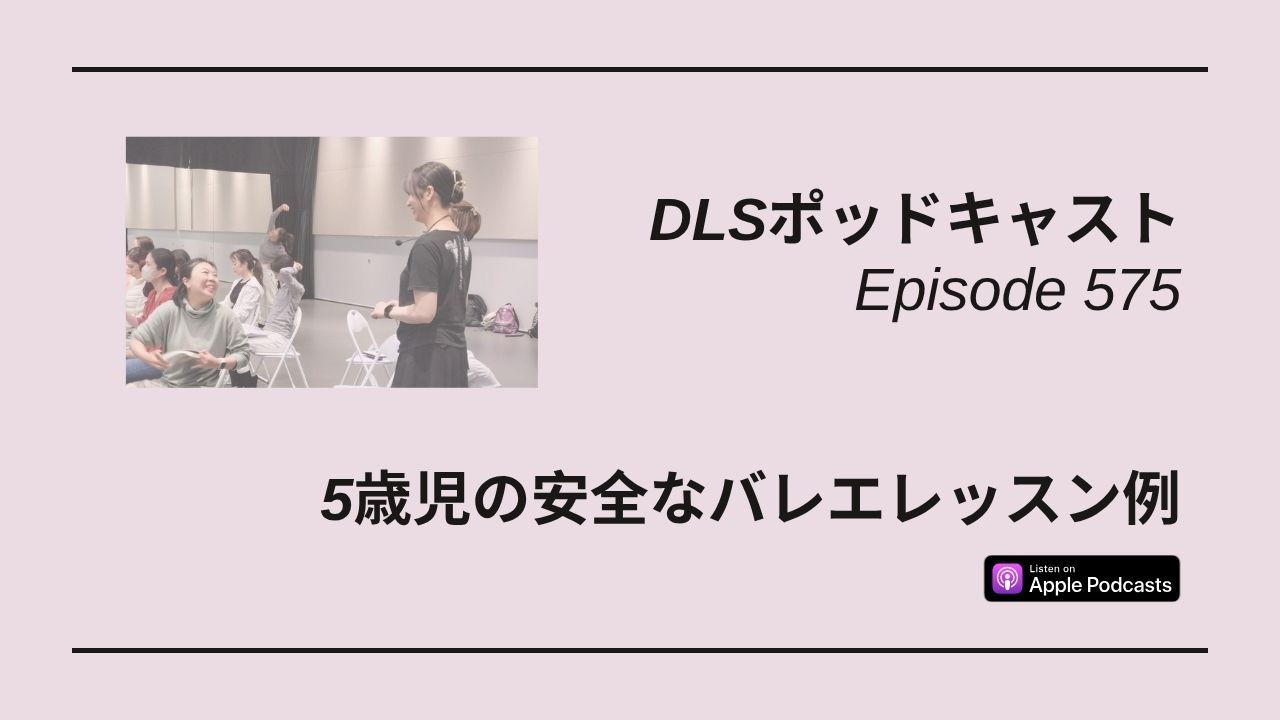バレエのウォームアップは、歯磨きと同じように早くから習慣づけたいもの。
5歳児の脳や運動能力の発達に合わせたレッスン内容、
安全に踊るための先生の準備を例と共に研究してみましょう。
Transcript
小さい時から活字中毒だった佐藤愛です。
活字中毒という言葉が存在するのかは分かりませんが、佐藤家ではよく使われていました。
朝ごはんは新聞と共に、という生活を学生の時からしていたし、
学校の図書室は大好きで、代本板という言葉の響きが大好きでした。
代本板ってわかります?
中学では使った記憶がないというか、学校の図書室の記憶がないので残念なんですけど、
私の小学校では、木の板に青いビニールテープが貼ってあって、そこに名前が書いてありました。
本を借りる場合、その本が置いてあった場所に、代わりに木の板を置くから、代本板。
たしか、本の後ろ側に小さな封筒みたいなのがついていて、
そこにカードが入っていたんですよね。
借りた人の名前と、借りた日にちが書いてあるの。
個人情報なんて無視した、とってもアナログなシステムだったと思うのですが、
ちょっとビンテージな感じがしません?
シリーズ系を借りると、毎回同じ名前が書いてあるので、
会ったことも、話したこともない、名前だけしか知らない人なのに
同じ本の趣味があるだけでちょっと親近感が沸いたりしてね。
現在でも本が好きなことは変わりないのですが、
本の楽しみ方が変わった感じはします。
例えば、ビクトリア州だけじゃないとは思うのですが、
私の住んでいる地域には図書館がいくつもあって、本に囲まれてお仕事をするのが好きです。
読むことはないだろう、膨大な量のストーリー達に囲まれているだけで、
幸せっていう良くわからない感覚があります。
確かに自分の本は翻訳版を入れたら6冊ですけど、
実際に本屋さんに並んでいるのは見たことないので実感がないから5冊?出しているけれど、
誰かが書いたストーリーっていうのが新鮮なんですよね。
図書館のアプリでは、オーディオブックを借りられるので、
本を読むより、聞く方が増えているかも。
ちなみに、最近よく読んでいる、聞いているのはcozy mysteryというジャンルの本ですが、
このジャンルが分かるよ!という人は、インスタのDMで教えてくださいね。
カンバーハウスにも、たくさんの本はありますが、
ほとんどがお仕事関係の参考書です。
解剖学関係の参考書って高いんですよ、1冊1万円以上はするの。
でも、この著者のセミナー受けるとなったら、1万円で足りるわけがないのだから、
それでもお得だと思って、どんどん買ってしまいます。
貯めているだけで楽しい、という不思議な楽しみ方をしてしまっていますが、本は使うもの。
ということで、今日のポッドキャストでは、私のコレクションの1つ
「Safe Dance Practice」(Human Kinetics社)のサブタイトルを日本語訳すると、
「実践的なダンス科学の観点」となる本より、
5歳児のバレエレッスン例をお話していきたいと思います。
ようやく、本題にたどり着いたね。
5歳のバレエと脳の発達と運動能力
エピソード573では5歳児の脳の発達を、エピソード574では運動能力を
それぞれエビデンスをベースにお話ししてきました。
まだエピソードを聞いていない人は、今日のエピソードの後でも大丈夫なので聞いてみてください。
5歳児の脳の発達で理解したいことは
- 象徴的思考(symbolic thinking)を始め、言葉や絵を使って物を表すようになる
- 言語能力や思考力は向上するが、まだ論理的思考は苦手
- 他者の視点に立つのが難しい(自己中心性)
- 保存の概念(constancy)を理解できない
でしたよね。
そこから考えて、
- レッスンで大切なこと
- 周りの大人が忘れないでおきたいこと
- 鏡やコンクール、理解力などで知っておきたいこと
をお話しました。
5歳児の運動能力の面では、移動運動スキルの発達順序と年齢目安を見ながら、
- どうして膝を伸ばす、つま先を伸ばす、が出来なくて問題がないのか。
- ポーデブラが出来なくて当たり前なのか。
- バレエステップより、ギャロップ、ホップ、スキップなどのコーディネーション力を育てることが必要なのか。
- くれぐれも、グランバットマンや大きなリープのあるジャンプをすべきではないのか?
をお話しました。
覚えてます?
今日はそれらのエビデンスベースの知識を踏まえ、実際にはどんなレッスンが適切なのか?
をお話していきたいと思います。
5歳児を安全に指導する先生のバックグラウンド例
先ほどもお話した、Safe Dance Practiceという本の、チャプター10は
特定の年齢層や身体的特徴に応じた指導
(原題:adaptations for specific populations)というテーマが書かれています。
その中に、ダンスレッスン例が書かれているので、ご紹介しますね。
まずは、先生のバックグラウンドから。
”スザンヌは地域のコミュニティセンターで、幅広い年齢の子どもたちにダンスを教えています。
彼女は子ども対応を含む応急処置講習を修了しており、
幼い子どもたちと安全に関わるために、
セーフガーディング(子どもの安全保護)に関する審査も受けています。
また、子どもの保護に関する専門的な研修も修了しています。
スザンヌは毎週のクラスの前に、
関連するリスクアセスメントや環境チェック、プロップ(小道具)の点検をしています。
また、生徒の保護者達と円滑な連絡を取れるよう、
そしてけがや病院搬送といった緊急時にすぐ連絡できるよう、
常に緊急連絡先を手元に置いています。
指導している年齢層が幅広いため、
各クラスごとに異なる計画や指導方法、安全な指導実践への配慮をしています。”
私も、政府認定バレエ学校で働いていたため、
スザンヌと同じように、厳しいチェック項目を受けていました。
例えば、1年に1度はCPRや応急処置のコースを完了しなければいけなかったし、
オーストラリアでは、working with children checkと呼ぶのだけど、
犯罪歴がないことを証明する、ポリスチェックを受けて、カードを持ち歩いていました。
ただ、バレエ学校では幼児は教えていなかったので、
幼児向けの特別な勉強、というのはしていませんでしたね。
今でこそ、ポッドキャストをはじめ、様々なところでお話している
SNSにバレエの写真を載せることへの危険性ですが、
バレエ学校時代は考える必要がありませんでした。
というのも、授業中に携帯を使う、特に生徒の写真を撮るなんてことはご法度でしたから。
ただ、治療家として放課後に働いていたときは、
生徒たちのプログレスを確認したり、エクササイズ宿題を出すために、
本人の許可を得たうえで写真や動画をとることはありましたけど。
セミナー資料で使う場合は、18歳以上、
つまり成人の許可がある場合か、未成年の場合は保護者の許可も聞いてあるもの、
学校側が宣材として、公式に使っているものなどを使っています。
日本のスタンダードだと、厳しく聞こえるかもしれないけれど、
”政府認定”という場所で働くためには、当たり前の安全確保なんですよね。
子供たちを守ることを第一にするのが、教育機関なので。
5歳児のバレエレッスン例
では次は、バレエレッスン例を見ていきましょう。
「Safe Dance Practice」はクラシックバレエだけの本ではありませんので、
原文はダンス、となっていましたが、
リスナーさんのほとんどがバレエ関係者だと思うので、
バレエ、と読み替えて聞いてみてください。
“4歳から6歳のグループでは、保護者はクラスに同席しませんが、
クラスの前後に子どもたちを送り迎えする必要があります。
これらのセッションは60分間です。
インプロ、創造性を育てるワーク、
イメジェリーやプロップを使ったダンスは引き続き取り入れられていますが、
基本的なテクニカル要素が楽しい形で導入され始めています。
スザンヌは、セッションの始めに慣れ親しんだ全身運動を使って穏やかに開始し、
動きの長さと強度を徐々に増していくこと、そしてセッションの終わりには
身体的にも精神的にもクールダウンの時間を取るようにしています。”
このセクションの前に3歳児クラスの説明があったので、
保護者のクラス同席やら、「引き続き取り入れられている」という表現がありますが、
できるだけ原文に沿って訳してみました。
インプロや想像力、イメジェリーという部分は、
今までの5歳児のバレエシリーズポッドキャストで勉強したことが入っていますよね。
インプロって何?と思う人がいると思いますし、私もシラバスを勉強するまでは
コンテのインプロみたいに創作ダンスのことかと思っていたのですが、
子供たちのクラスでインプロという場合は、
音楽に合わせて、好きなように表現する。という感じだそうです。
DLSワールドでは”われらが校長先生”、
シラバス創立者のクリスティンと長い間仕事ができた私は、
シラバスを作った人に実際に質問したり、
彼女がどうやって評価しているかを直に見てくることができたので、
本当に良い勉強をさせてもらったんだけど、
彼女が彼女のシラバスのなかで”インプロ”を見ているときには、
- 音楽の雰囲気が理解できている
- 音楽のフレーズが理解できている
- 同じ動きの繰り返しではなく、様々な動きが入っている
などを見ているんだそうです。
昔の記憶なので、一語一句正しくないかもしれませんが。
プロップというのは、エクササイズの世界ではエクササイズバンドとか、ボールなどを指しますが、
BCシラバスでは、お人形、小さなかご、
もう少しレベルが高くなると扇子なんていうのも使うようになっていましたね。
5歳から学んでおきたいウォームアップとクールダウン
エクササイズ指導者の私が、5歳児のバレエでカギとなること、
そしてDLS公認アドバンスドインストラクターコースでもお話していることの1つに
このレベルでもウォームアップやクールダウンが必要、というものがあります。
エクササイズの世界では、
- ウォームアップはその後にくるエクササイズに備えて行うもの
- クールダウンは、心肺機能やリカバリーのために行うもの
となっています。
でも、この年齢の子たちのレッスン例を見てわかるように、
そんなに運動量は多くないし、レベルの高い動きはしていないはずなんですよ。
では、どうしてウォームアップやクールダウンが必要か?
それは、”安全なバレエのレッスン”の習慣化です。
歯磨きで考えてみましょう。
いくらきれいにしていても、乳歯は結局抜けちゃいます。
だから歯磨きが必要ない、ということもできるかもしれません。
だけど、幼いころからごはんを食べたら歯磨きする。と習慣化しておけば
大きくなった時に、自分でできるようになりますよね。
好きか嫌いかは別だし、面倒くさいと思うのは変わらないと思うけど。
子供たちのウォームアップやクールダウンとは、こういうこと。
- バーにぶら下がってはいけませんよ
- 鏡に触ってはいけませんよ
- バーを持つときは、親指は下に回しませんよ
- 髪の毛はお団子、もしくはしっかりとまとめますよ
こういった、スタジオ内のルールというのでしょうか、そういうものと一緒に
すでにやったことがあるけど、全身を使う運動をしてからレッスンがはじまること。
レッスンの終わりはゆっくりな動きに戻ること
というのが”当たり前”になっていたら、もう少し高いレベルになった時に、
「アップは自分でやっておきなさい」が通じます。
ですが、「体が柔らかいうちに」という解剖学的に意味の分からない理由とともに、
子供たちのレッスンの最初で床でストレッチばかりしていて
ある程度のレベルになったら
「レッスンの前に、自分でアップしておきなさいよ」と言われたら、
彼らは何をすると思います?
そう、床でのストレッチ。
それがバレエだと、幼いうちから教えられてきたのだから、仕方ないでしょうね。
先生に、しっかりとウォームアップしなさいよと言われたら、
しっかりとストレッチ、つまりスプリッツや開脚、エビぞりで、
できる限り大きなストレッチをすることだと理解してしまって、仕方ないでしょうね。
小さい時から安全な習慣を
私が何十年経っても覚えている図書室の雰囲気、
本を読むのは楽しいという感情、
同じように本を読んでいる人との妙な親近感。
こういうのと同じように、
- 幼い時のバレエレッスンの雰囲気
- 楽しい、もしくは先生が怖い、バレエは痛いという感情
- 同じようにバレエを習っていた人とは、何か話すことがある
というのがあると思うんですね。
たとえプロにならなかったとしても、バレエは小学校でやめてしまったとしても。
だからこそ、私は
- スタジオが楽しい場所であること
- バレエが楽しい経験であること
- 安全に踊る知識が習慣化していること
は非常に大事なのではないかと思っています。
- 歯磨き、トイレの後の手洗い
- 知らない人に声をかけられても、ついていかない
- 右、左をみてから道は渡る
こういった、子供たちに話すルールは、彼らが100%理解できていなくても大事。
というのは、保護者ならみんな分かること。
ぜひ同じように、生徒の安全と将来の健康を第一に考えるレッスンを
提供しているスタジオや先生を選ぶようにしてあげてください。
- どれだけプロを育成しているか
- 生徒数がいるか
- 留学生がいるか
などが大切だと思う人もいるとは思うの。
だけど、5歳児の脳の発達、運動能力の成長を考えると
本当に大切なものが見えてくるんじゃないかな?と思います。
もう少し勉強したい方は、
「保護者が知っておきたい成長期の体」オンデマンドセミナーをどうぞ。
先生たちは、こうやって勉強すれば、
よりよい指導を提供することができるようになると思います。
いつものレッスンを少し変更するだけでも、
安全な、年齢に見合ったレッスンができるようになると思います。
エクササイズの勉強をしておけば、
たとえエクササイズクラスを指導しなかったとしても、
安全なレッスンの指導の1つである、
ウォームアップやクールダウンなどが提供できるようになるはず。
DLS公認スタンスインストラクターは、毎年6月より10か月のみっちり勉強コースです。
次回の申し込みは、来年になってしまうけれど、
今のうちに、コース資金を貯めたり、できる範囲で勉強をスタート、
ボディコンサークルなどで、ダンサーに特化したエクササイズを継続して受けることで
エクササイズの効果を体験したり、エクササイズに慣れてみてください。
Happy Dancing!