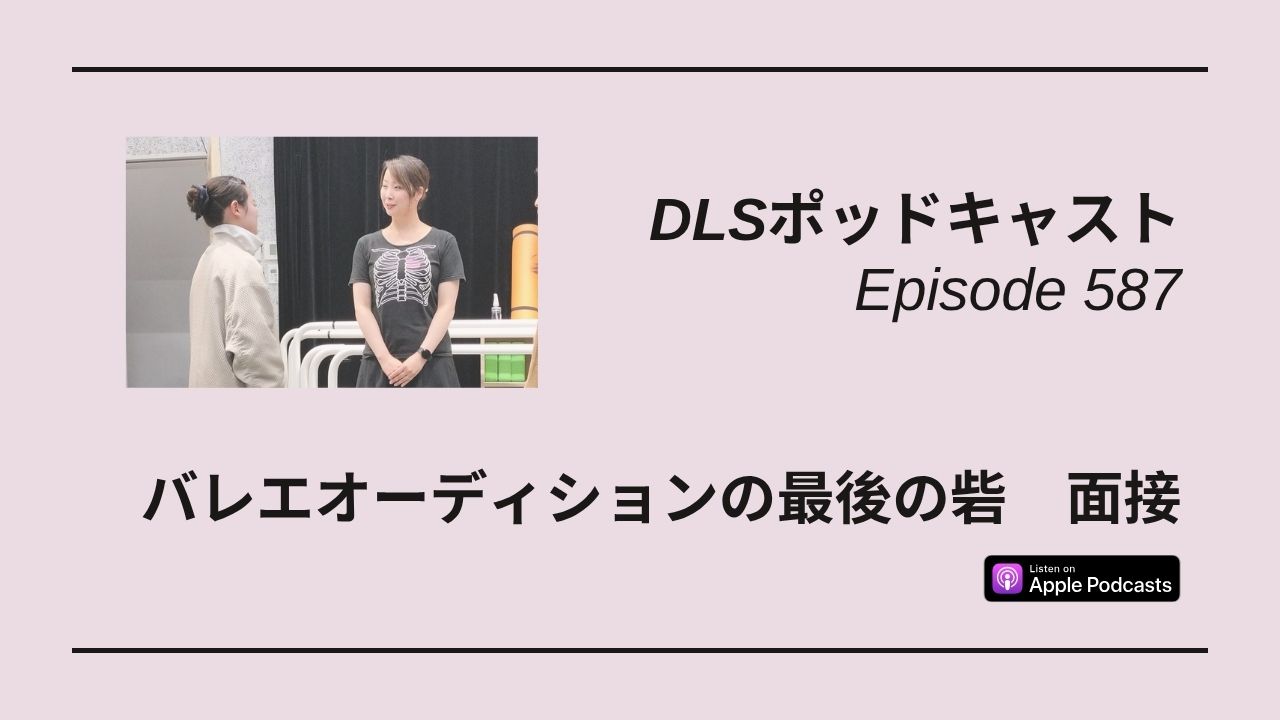バレエ団のオーディション、最後の壁は面接。
技術だけでなく、性格や文化理解が見られるって知っていましたか?
留学やオーディションについて考える前に、
面接の前に必要な準備について一緒に考えてみませんか?
Transcript
オーストラリアのバレエ学校に留学した際、
グループ面接はただのおしゃべり時間だと思っていた佐藤愛です。
2003年なのでかなーり前の話になりますが、
リニューアルしてきれいになったり、
増設される前の新宿村スタジオでオーディションがありました。
一日かかるオーディションで、
最初のクラスがクラシックバレエレッスン、
次がポワントで眠りの1幕のバリエーション途中まで。
これらのクラスはDLSで「われらが校長先生」と呼んでいる
クリスティン・ウォルシュ本人がクラス指導をしてくれました。
次はコンテンポラリー、これはバレエ学校の共同ディレクターである
リカルド・エラ、通称リッキーが指導してくれました。
クリスティンは、生徒たちにミズ・ウォルシュ、
ここでのミズは先生という意味ですので、
ウォルシュ先生と呼ばれることも多くあったのですが、
なぜかリッキーはミスター・エラとなることはなく、
いつでも、誰でもリッキーと呼んでいましたね。
オーディション後、ひとりひとり呼ばれて二人と面接があり、
結果と留学前に何を努力すべきかなどを言われました。
私の場合は、2年生に飛び級できるという話と、「痩せなさい」と言われました。
ここからずーっと「痩せなさい」という言葉と戦うことになるのですが、
それは今日のテーマではないので飛ばします。
実はね、その後に留学許可が出た子たち全員が集まって
グループディスカッションがあったんです。
でも内容は留学準備はどーのこーの、みたいな話で、
みんな私服に着替えてもいたので、
当時の私はただのオリエンテーションだと思っていました。
今でも覚えている質問で
「オーストラリアの首都はどこか知ってる?」というのがありました。
さて、ここで皆さんに質問です。
オーストラリアの首都はどこか知っていますか?
3,2,1…
答えはシドニー!ではなく、メルボルンでもなく、キャンベラという場所です。
本当かどうかわかりませんが、その時に言われたのは
シドニーとメルボルンが首都争いをしていたので、
真ん中にあったキャンベラになったっていうね。
もちろんこの段階では留学許可が出ているので、
グループ会話がうまくいかなかったからといって判断が変わることはなかったとは思います。
でも今思えば、このような会話の中で
どれだけ英語が分かるかを見ていたんじゃないかな?と思います。
だって留学後、何人かは英語のクラスを受けなければいけない事になっていましたから。
さて今日のポッドキャストでは、
先週ご紹介したデンマーク王立バレエ団のオーディションプロセスについて、
芸術監督のAmyのインタビューを分析しています。
お伝えしておきたい注意事項や、オーディションの流れは、
先週のエピソードですでにカバーしたので、まだ聞いていない人はそちらからどうぞ。
今日はオーディションの最後の段階である、面接についてお話していきたいと思います。
オーディションの最後は面接
私のオーディション経験でもそうですし、
バレエ学校卒業後通訳として立ち会ったオーディションでもそう。
ローザンヌ国際バレエコンクールの分析をした
エピソード498、「ローザンヌ国際バレエコンクールでも足を見る」でもお話しましたよね?
バレエオーディションの最後は、99.9%のケースで面接です。
ディレクターのAmyによると、2日間カンパニーレッスンを受け、
フィジオで健康チェックが入った後に、20分の面接が行われるのだそうです。
つまり、ディレクター本人と一緒に20分お話するということ。
インタビューの中で、どんな質問をするのかもお話されていました。
どんなバレエ学校、バレエ団でも聞かれると思われる
「なぜロイヤル・デンマーク・バレエなのか?」という質問や、
このバレエ団にとって大切なポイントである
「ブルノンヴィルについて何か知っていますか?」という質問があるそうです。
カンパニーのレパートリーについて聞かれることがあるのは、想像しやすいと思うけれど、
こういう質問への準備を、オーディション準備に入れておかなければいけませんよね。
文化の違いとバレエ団
彼女が「本当に重要なこと」と念を押した面接質問に、
「私たちのカンパニーが安全で繁栄する環境を持ち続けるために、
あなたは何を提供できますか?」というものがありました。
安全な環境、という言葉があったことが私は嬉しかったのですが、
カンパニーが安全な環境を提供するだけでなく
「安全で、繁栄する環境を持ち続けるために」ダンサー側も努力する必要がある
という前提があるということですよね?
この質問、会話の中で彼女が見ているのは
チームワークを大切にするダンサーなのか、それとも、
自分自身がスターになりたいという欲望について話しているのか?という点だそう。
面白いことに、その後の会話でデンマークや北欧文化は、
北米、つまりアメリカ合衆国とカナダとは異なるという話に進んでいます。
会話の内容から、アメリカでよく見られがちな、個人主義、スター志向と、北欧文化、
そしてこのカンパニーで求めているものは異なる、と言っているのではないか?と思われます。
私も昔そう考えていましたけど、
日本で海外というと、直接的ではないものの、アメリカを指すイメージが強くないですか?
- 海外の人はものをハッキリ言う
- 海外の人はsorryと言わない
という感じと言うのでしょうか?
日本にいるときに
「海外のコンクールに出るなら、周りを押してどんどん前に出ないと!」
なんて言われたこともあります。
でも、海外生活20年以上、英語圏だけではありますが、
様々な国のテレビや雑誌、情報を見ていると
ステレオタイプの”海外”というものが、
アメリカ合衆国だけを指しているのではないか?と感じることがあります。
しかも、その中でもNYとかシリコンバレーなど、アメリカ全土ではないとも思います。
例えば、オーストラリアはchill文化とかlaid back文化があると言われるのだけど、
ガツガツしてなくて、ゆったりと構えている感じが
良いというか、良く見られる文化だと言われます。
だからこそ、大都市シドニーの人たちは、
いつも焦ってるし、性格が悪いなんて言われますが、
東京と比べると、シドニーのゆっくりしていることったら!
北米というとアメリカとカナダを指しますが、
カナダ人は「sorry」とよく言うとジョークになるくらいです。
先週のエピソードで、今月のメインテーマ、
バレエ団ディレクターの話に行く前にお伝えしておきたい2つのポイントの中で、
海外という言葉についての注意事項をお話しました。
海外が偉い、正しい、ということはないし、
海外と言った場合、日本以外のすべての国が同じなわけではない
ということもお話しましたよね?
多文化を理解し、尊重する考え方がないと、
このようなオーディション面接で「良かれ」と思って言ったこと、
例えば”海外ダンサーのように”前にプッシュしなきゃ!という”努力”で伝えた言葉が、
面接の結果に影響してしまうかもしれません。
自分で考えられるダンサーになろう
Amyは「デンマーク社会の中でどのようにそこに適合するのか?ということを見ている」
とも話しているので、ダンサーの性格というか、
適合性はカンパニーにとって大切なことなんだと思います。
特に日本のダンサーと話していると、
- どのバレエ学校でもいいから留学したい
- どのカンパニーでもいいから仕事が欲しい
という人たちが多くいるように感じます。
もちろん、狭き門であるバレエダンサーという職業を考えたとき、
まずは仕事を手に入れることが大切だというのもよくわかります。
今までの人生のほとんどを、バレエトレーニングに費やしてきて、
そのためだけに努力してきたのだから、どこでもいいから入れて!
と考える理由もわかります。
先週のエピソードでお話したように、
付属のバレエ学校がある場合、オーディションではそこの生徒たちが優遇されやすいので、
早くからバレエ学校に入ることで、すべてが安泰だと思う保護者がいるのもわかります。
だけど、その国の文化、一緒に仕事をする人たちとの相性ってとても大切だと思うんです。
それがうまくいかないと、ホームシックになったり、精神的に疲れてしまって、
バレエ学校を辞めていくダンサーをたくさん見てきました。
日本人留学生だけでなく、地方から出てきた現地生徒もそうなんだけどね。
このポッドキャストを聞いてくれている人たちの多くは、
バレエ学校留学を考えている子供を持つ保護者や、
留学したい生徒がいるバレエの先生だと思うので、
バレエ学校にフォーカスしてお話しますけど、
バレエ学校とは、ダンサーを育てる職業訓練校なんですね。
だから、テクニックが完璧でなくても、
ポテンシャルがあれば留学許可がでることが多いです。
ポテンシャルとは何か?
今回のAmyの話では
- 音楽性、特に音楽的にチャレンジできるダンサー
- コーディネーション力
- 文化に対する理解
- ダンサーの性格
が上がっていました。
そして
- このインタビューが英語で行われていること
- オーディションビデオの内容説明のサイトが英語であること
- オーディション資料受付情報が載っているサイトが英語であること
- オーディション最後が、ディレクターと20分の面接であること
より
- 英語が分かること、会話ができること
- 英語で調べられること
- 英語で自分の意見を述べられること
はとっても大事な力になるのではないでしょうか?
基礎レッスンを見られるところからスタートし、面接で終わる。
つまり、基礎が出来ていなければ次のステップには進めないですし、
いくら踊れても面接で落とされる可能性があるということ。
だとしたら、基礎練習は勿論ですが、
会話の練習もダンサーにとって非常に大事なレッスンになるのではないでしょうか?
母国語で自分の意見が話せる?
確かに「英語が分からなくても、雰囲気で通じるよ!」というのは、本当なんですよ。
例えば、私は東京生まれ、千葉育ちでオーストラリアに来ましたから、
現地の子たちのように英語が母国語ではありません。
でも、バレエ学校の講師として彼らのエッセイや、筆記試験を見ていると
- 文法が分かっていない
- スペルの間違いがある
- 自分の言葉で説明ができない
という子たちが多くいることに気づきます。
日本人だからといって完璧な文法で、漢字がすべて書ける
わけではないのと同じなんでしょうね。
だから英語圏で育ったから、英語が教科書通りに完璧なわけではないんですね。
それでも通じるのだから、私たちがブロークンイングリッシュで話しても通じます。
とはいえ、学校や会社の面接で
「ちょーやばい」とか「しゃばい」なんて言わないでしょう?
例が古いって?ごめんなさいね。
意見を聞かれて「私わかんないっす」って答える人と、
たとえ緊張して言葉に詰まったり、文法が正しくなくても、
「私はこう思います」と伝えられる人、
どっちの方が面接に受かると思います?
こんな話もありました。
メルボルンにロシアのツアーバレエカンパニーが来ていたとき、
けが人が多くて現地のダンサーのオーディションがあったんですね。
そこに友達が参加していました。
彼女はウクライナ人なのでロシア語が分かります。
彼女が言うには、一緒にオーディションを受けた子たちの中で、
ロシア語が分かるのは彼女だけだったとのこと。
ロシア語が分からないからオーディションに落ちることはなかったけど、
ロシア語が分からない人たちの給料はぼったくりのような金額で、
ロシア語が分かる彼女は、ほかのダンサーたちと同じだけの支払いがあったとのこと。
さっきもお話したように、
どんなカンパニーでも、アパレンタスでも入りたい!
と思うダンサーや保護者が多いのはわかります。
無給料で働いて、好きになってもらえたら、正式にオファーが来るかもしれない
という期待もわかりますし、そういうケースも実際にあると思います。
でもね、カンパニー側もそれを知っていることが多いんですよ。
だから、意見を伝える力がないと、
使えるだけ使われて終わり、となっても気づかないかもしれません。
何よりも、英語の得意不得意と関係なく、母国語で自分の意見を伝える練習は
今からでも、何歳からでもできると思います。
分からないこと、不明な点を「分からないので説明してください」と言えるとか
「私はこう思います」という考えを、先輩や先生に伝えることって、
英語が出来たら自動的にできるようになるわけじゃないでしょう?
協調性とは、自分の意見を言わず、周りの言いなりになることではなかったですよね?
異なる価値観や立場、意見の人とコミュニケーションを取り、
協力して目標を達成できる力ではありませんか?
そう、協調性を持つためには、
まず自分の価値観、バリュー、意見を持つ必要があるんですよね。
バレエのためにも、できる大人になるためにも、
こういうところの努力を忘れないでほしいなって
留学生を受け入れてきた経験がある私は思っています。
来週もデンマーク王立バレエ団のディレクターインタビューより、
バレエ団員の契約や仕事量、お給料についても調べてみましょう。
Happy Dancing!