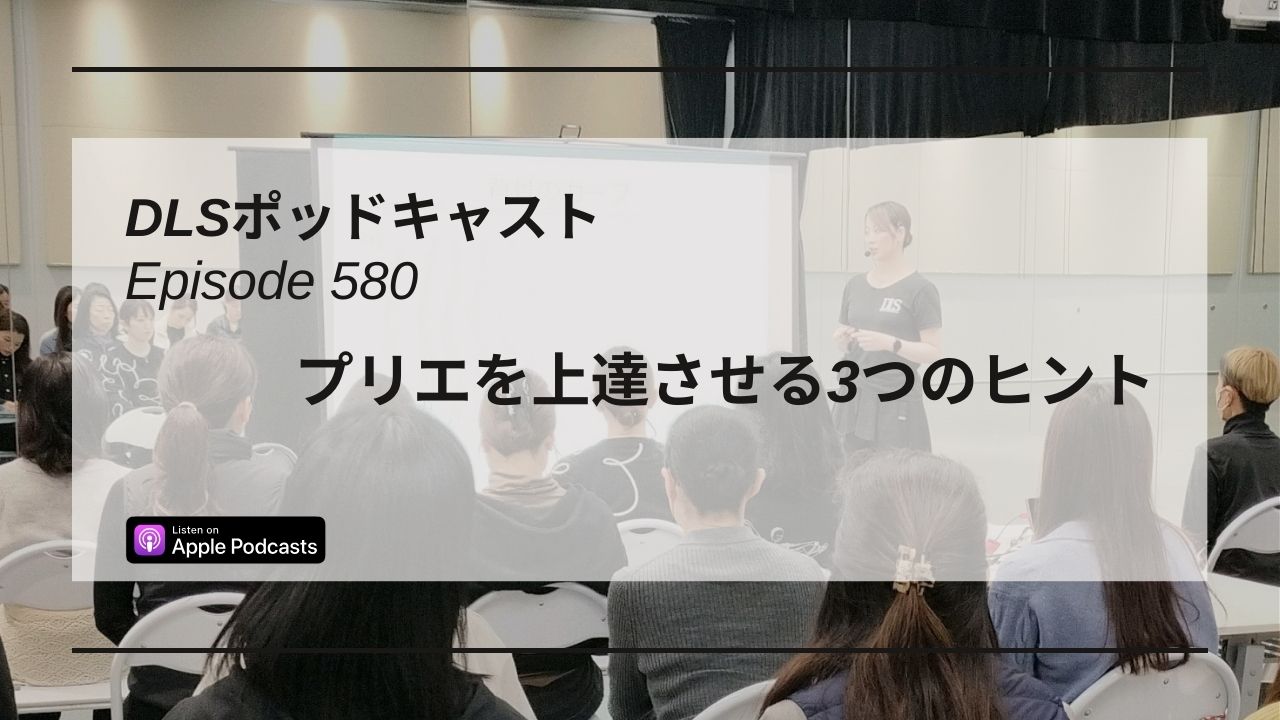バレエ初心者でも、現役プロダンサーでもバーレッスンの最初に行うプリエ。
プリエを上達させる3つのヒントをお話しました。
プリエが出来るようになると、踊りが変わるよ!
Transcript
プリエで1冊書いたのに、まだまだ話し続けることが出来る、
自分のマニアック度にビックリしている佐藤愛です。
バレエが好きだから、バレエの世界の仕事をしているというより、
バレエ分析が好きだから、マニアな話をしている
という表現の方が正しいんじゃないか?なんて思ってしまいますよね。
ま、バレエには様々な楽しみ方があるんだと思います。
日本でバレエを見に行くと、観客席のほぼ全員がバレエ関係者だなと気づきます。
ターンアウトして立っている姿はもちろん、
お団子のままだったり、スタジオのお友達と一緒にいる様子が見えるからです。
メルボルンでバレエを見ると、そしてこれは、私が見に行く種類のせいかもしれませんが
もちろん、バレエ人口もいるのだけど、それと同じくらいシニア世代がいます。
1年シーズンパスを買って、数か月に一度お友達とご飯食べて、
シャンパン飲んで、バレエを見るイブニング、みたいな感じ。
話している内容も、バレエ人口とは異なって面白いです。
バレエ人口は、誰のつま先が良かったとか、細かったとか、テクニックの話が多いけど、
シニア世代は、衣装が良かったとか、ストーリーが分かりづらかったとか。
同じバレエでも昔のOOプリンシパルを見た時はこうだったわよねー
みたいな歴史の話が出てくることも。
どっちが良い、悪いではないですよ。
ただ、もしバレエを勉強している人達がテクニック「だけ」見ていて、
バレエ愛好家が全体を見ていたとしたら、
バレエに通じているのはどっちだろうか?とは考えてしまいますよね。
その背景には、
「レッスンではいつも、自分の出来ないところだけを言われる」
という昔からの習慣があるからかもしれません。
バレエとは、出来てない部分、完全でない部分を発見するものだ。
と子供達に教えてしまっていないか?
というのは、注意したいところですよね。
とはいっても、日本でバレエを見ていると
テクニックや体型について色々と言っているのは、
大人バレエ生徒さん達の方が多い場合もあります。
そういう楽しみ方なのかもしれないけれど、
誰かのネガティブな部分を探すのが楽しいとしたら、
ちょっと性格的な問題があるんじゃないかと思ってしまいますね。
もしかしたら、自分で稼いだお金なんだから、「完璧」が見たい!
のかもしれませんが、
生の芸術は、その時の不完全さも含めて、リアルなんじゃないかなーなんて思ったり。
そういう私も、バレエを見たらダメなところ、いっぱい見えます。
- この子、こうやってトレーニングしたらもっと踊れるようになるのに
- このカンパニーはこういう注意だけされてきたな
- ここのミストレスは、これが好きなんだな
なーんていうのが見えますんでね。
最初に言ったように、私もバレエが好きなのではなく、
分析が好きな人間の一人なんでしょう。
さて、今月は基礎に戻ってプリエについてお話してきました。
順序だててお話しているつもりなので、順番に聞いてくださると嬉しいです。
もちろん、このシリーズの感想もお待ちしておりますよ。
インスタDMで今度のシリーズは、これを取り上げてね!
なんてリクエストも受け付けております。
最終回の今日は、プリエを上達させる3つのヒントをお話します。
もちろん、プリエが使えるようになるための知識は、
100ページ以上+エクササイズの説明動画と共にお話していますが、
今日はそこから、今月お話してきた内容とつながりのある3つのポイントをお話しますね。
プリエを上達させるヒント その1:深さにこだわらない
最初からお話してきましたが、
「プリエは深ければ深いほど良い!」という思い込みを捨てましょう。
深いプリエと高いジャンプは必ずしも一致しません。
深くプリエが出来たら、軽く飛べるとも限りません。
バレエで必要な可動域全てと同じく、
「練習するから上達する」という順番を忘れずに
先生なら正しいプリエを指導してください。
ダンサーなら、正しいプリエを学んで、練習してください。
深くしなきゃ!と力むと逆効果ですし、
プリエの浅い理由を理解していなければ、あてずっぽうストレッチは無意味です。
なので、考え方から変えていこう。
- 深さではなく、使えるプリエにフォーカスする。
- 可動域だけに執着するのではなく、順序だてて使える関節や筋肉を育てる。
これなら、みんなできそうでしょう?
正しいプリエが何か分からないなら、正しい練習は出来ませんよ?
正しいプリエと間違ったプリエのチェックリストや、
どうやってプリエを育てる指導をするか?は
教師の為のライブラリ「前方インピンジメント&プリエの浅い子」
を参考にしてくださいね。
プリエを上達させるヒント その2: プリエでホールド
エクササイズを勉強していない人達に、
「可動域だけに執着するのではなく、順序だてて使える関節や筋肉を育てる」
と言っても、何をしたらいいのか分からないという人もいますよね。
もちろん、DLSでは公認スタンスインストラクターコースを行っていて、
そちらを卒業したら、つまり立ち方とターンアウトを指導できるようになったら
プリエ本と上半身本、そしてクララで連載していたエクササイズ達を
指導できるアドバンスドコースがあります。
でも、今年の申込は既に終わっちゃったからね。
どうやったら、順序だてて使える関節や筋肉を育てることが出来るのでしょうか?
一番簡単な答えは、プリエでホールドする振付を多く取り入れること。
プリエの練習は、バーレッスンの一番最初だけではありません。
フォンジュの柔らかいプリエだけではありません。
- 浅いプリエでホールド
- 深いプリエでホールド
- 早いプリエでホールド
- ルルベではなく、片足プリエでバランスをとる
- アレグロ終わって走るだけ~ではなく、ジャンプの着地で4カウントくらいホールドし、正しくポジションに戻ってくるとこまでを振付に入れる
柔らかい両足地面のバーレッスンプリエでケガするダンサーはいません。
ケガを予防するために、深いプリエが必要だと仮定するならば、
ケガしやすい動きを、安全にこなせるための準備が必要です。
このようなプリエホールドが出来ないなら、トウシューズは履くべきではないけれど、
だからこそ、ルルベの高さとか、しなる膝とかの前に、
ちゃんと練習しておきたい部分ではないでしょうか?
深いスクワットは、浅いスクワットより筋力が必要、でしたよね。
プリエを上達させるヒント その3:筋トレ
プリエでホールドが下半身のトレーニングだとしたら、
プリエを上達させるヒントは、体全体だと思ってください。
プリエは股関節、膝関節、足首とフットの部分で動きが生まれますが、
股関節とは、大腿骨と骨盤で出来た関節。
骨盤を安定させる筋肉はもちろん、プリエでも保てるターンアウトの筋肉、
骨盤の上に乗る背骨を正しく使える筋肉や、ポーデブラの動きに負けない肩回りなど。
プリエ単体が問題ではなく、レッスンで使えるプリエを手に入れたいんでしょう?
片足になるとプリエが硬くなったり、アレグロになるとかかとが浮いちゃうんでしょう?
ジャンプの着地が煩いんでしょう?
これらは全身の問題です。
そのため、ダンサーに特化したエクササイズが必要だって気が付いて。
柔らかいプリエとか、ソフトな着地とか言うと、
言葉の関係か、柔軟性、つまりストレッチすればいいのねー
と思ってしまうダンサー、保護者、そして先生たちがいますが、
柔らかく使うというのは、「使う」がカギ。
強く使う、シャープに使う、などと同じように、柔らかく使う、も筋肉の仕事です。
ここに追加するとしたら、コーディネーション力も必要になってきます。
さっきも言ったように、レッスンで使えるプリエの為には全身が必要なので。
だからこそ、幼稚園クラスの時から、徐々にコーディネーション力を育てていきたいんですよね。
8月のポッドキャストでは、5歳児に必要なバレエレッスンをテーマにお送りしていますので、
そちらも忘れずに聞いてくださいませ。
使えるプリエを目指そう
ということで9月はプリエについてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか?
9月1回目のエピソード、577でお話したように、
この仕事を長くしていると、「もうすでに知ってるよね?」と思ってしまう部分があります。
今月のポッドキャストシリーズが、基礎を振り返るお手伝いになりますように。
そして、知識として知っていても、レッスンで最近とりいれていないな、と気づいた先生は、
是非レッスンプランを見直してみてください。
既に知ってるよね?と思わずにお伝えさせていただきます。
DLSにはダンサーに特化したエクササイズがオンラインで受けられる、
ボディコン エクスプレスというクラスがあります。
ボディコン、とはボディ コンディショニングの略、
エクスプレスとは、特急という言葉で、
専門的なコンディショニングエクササイズが、
ささっと30分でできちゃうよ!というクラスです。
週に5クラス、時間帯も様々ですから、
自分のスケジュールに合わせてトレーニングしてください。
バレエダンサーは勿論ですが、
デモンストレーションをしなければいけないバレエやダンスの先生たちにもおススメです。
先生が怪我したら、生徒にクラス提供は出来ませんし、収入にも影響するでしょう。
車のメンテナンスと同じように、必要なものの1つとして、
お仕事の時間と考えて、スケジュールを確保してくださいね。
クラスの詳細はDLSサイトより。
今月のポッドキャストで何度もお話した、教師の為のライブラリも
気になったらサイト内で覗いてみてください。
ダンサーに見られやすいケガはもちろん、
今回のようにプリエの確認などテクニック的な部分も勉強出来ます。
今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。
また来週、金曜日のポッドキャストでお話しましょう。
Happy Dancing!