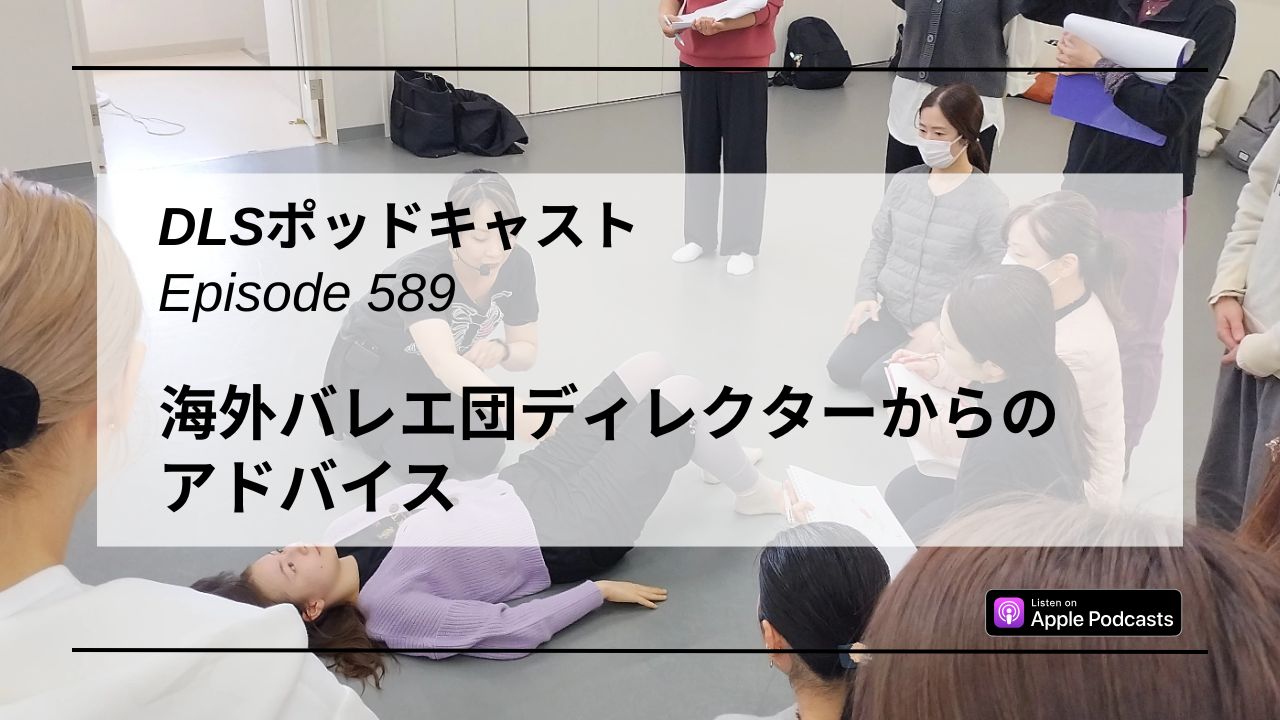バレエ留学&海外で踊りたいダンサーは必聴!
海外バレエ団ディレクターが、バレエ団に取りたいダンサーについて教えてくれました。
ダンスの先生たちも聞いておこう。
Transcript
多くの英語圏がディレクター、ではなくダィレクターと発音する
ということに気づいたのはオーストラリアに留学してからだった佐藤愛です。
Directorというスペルなので、Diをローマ字読みして”ディ”になったのではないか?
というようなことがネットに書いてありましたが、よく分かりません。
発音とは面白いもので、国によって「正しい」が異なります。
英語圏でもブリティッシュ・イングリッシュを多く使うオーストラリアですが、
オーストラリア訛りがありますし
お隣のニュージーランドの発音は、まったく違って聞こえます。
ハリウッドの俳優さんたちの英語は
あえてアクセントがないように作られた「ハリウッドアクセント」だそうで
一般の人たちが使っている発音ではないんですって。
特にガラコンサートの裏で働くと、様々な国のダンサーと出会いますし
共通会話は英語になるのですが、国によって発音が大きく異なります。
私が特に苦心するのは、アメリカンイングリッシュ。
とはいえアメリカも大きく、場所によってアクセントは異なりますので、
どのエリアなのかに左右はされますが
昔サンフランシスコで踊っていたというダンサーのアクセントは
本当に分からなくて苦労しました。
英語をしゃべるなら、発音が良くなくっちゃ!
と言われることが多いと思うのですが
国によって発音が異なるし、訛りはあるし、スペリングも変わります。
しかも、カッコいいとか、セクシーなアクセントなんて言われることもありますので
発音なんて気にせず、コミュニケーションをとろうとする勇気が
大切なんじゃないかと思っています。
今日のポッドキャストは発音についてがテーマではありませんでしたよね。
今月シリーズでお届けしている
私たちが知っておきたいこと、考えたいことをピックアップしてきました。
エピソード586では
オーディションに申し込む方法と、どのような内容が見られているかの話。
エピソード587では
オーディションの最後の砦となる、面接について。
バレエ団員のスケジュールやお給料についてを見てみました。
最終回の今回は、ディレクターがお話していた
若いダンサーたち、オーディションを希望しているダンサーたちへの
アドバイスについてを見ていきたいと思いますが
もし今までのエピソードを聞いていなかったら
今日のエピソードを聞いた後でも大丈夫なので、586から聞いてみてください。
芸術監督の考え方が見えるので
今日のアドバイスへの繋がりやバックストーリーがより感じられると思います。
芸術監督からのアドバイス その1:リサーチ
1つ目のアドバイスは「リサーチをすること」だそうです。
カンパニーに入りたいなら、そのバレエ団が何を踊るのか
レパートリーは何か、振付家や歴史を知ってください。と言っています。
プロダンサーとしての生活、カンパニーライフはただの仕事ではなく
ライフスタイルであり、文化であり、家族であるというのが彼女の意見です。
エピソード587のオーディションの最後の面接についてでもお話しましたが
彼女はカンパニーメンバーの文化やバレエ団に対する理解を大切にしているようですよね。
それもそのはず。
エピソード588でお話したように、デンマーク王立バレエ団は年間100以上の公演があります。
それだけの舞台をこなすためには
レッスンやリハだけでなく、長い時間一緒に生活する必要があるんでしょう。
舞台裏の雰囲気は多分、舞台上のケミストリーにも影響するでしょうから
良い舞台を作るためには大切なポイントなのかもしれませんね。
芸術監督からのアドバイス その2:健康
2つ目のアドバイスポイントは「自分をケアすること、大切にすること」でした。
しかも「精神的にも肉体的にも、自分が良い状態にあるように」だそうです。
バレエダンサーとは大変で
短いキャリアだからということや、何か壁にぶつかっても立ち直れるためにも
心と体の健康を維持するようにと話していました。
ポッドキャストのイントロでもお話してますけど
「生徒の安全と将来の健康を第一に考えるレッスンを”当たり前”に」
というDLSのスローガンは
肉体労働であり、競争の激しいバレエ界で生きていくためには
基本となる部分なんですよね。
みんな、基礎というと
ターンアウトとかつま先、体型やら柔軟性などを考えるようですが
そして、小さい時から練習すれば
それらを手に入れられると思っているようですけど
ダンサーという言葉は「踊る人」という意味で
「踊ることが出来る人」でいるためには
動ける体と心を維持し続けなければいけません。
基礎体力、筋力、メンタルヘルス。
これらが大切だというのは、もう600エピソードに近いポッドキャストでも
12年半やってきているDLSの活動でもご存じだと思いますけど
ダンサーだけでなく、先生たちも仕事をこなすうえで必要だと思います。
もちろん、毎日動いている職業なので
椅子に座っている会社勤めの人よりも体力や筋力はあるかもしれませんが
比較材料が同い年の座っている人では困ります。
自分のキャリアのためにも
先生たちは週に1-2回は自分のためのエクササイズを受講した方が良いですよ。
レッスンではなく、エクササイズとお話した理由は、
- 昔の怪我や痛みを心配することなく受けられる
- 1時間45分のレッスンより手っ取り早い
- クロストレーニングとして、いつも行っている動きとは異なるものを選択する方が健康的
の3つの理由があります。
なんでもネガティブに受け取る癖があるなら
それもメンタルヘルスの一環として考え方を修正する必要があるでしょう。
ダンサーも先生も、もちろん保護者もそうなんですが
誰かからアドバイスやフィードバックを受けたときにどう受け取るか?
は、その人の器や成長のポテンシャルを見せてくれると思います。
私も、DLSのインストラクターコースやアドバンスドコースで
何か月も同じ人たちと時間を過ごしていますが
精神的に成長している人は、試験の点数も良いです。
周りの人が一緒に練習したいと思う様子も見えます。
この素質は生徒がそのスタジオにいたいと思うのと一緒なので
先生たちにとって非常に大事だと思います。
逆に愚痴を言う人たちは、孤立してしまう様子も見えます。
大変な時に、愚痴りたいのはよくわかりますし
それがダメなんじゃないんですが
同じコース、スタジオ、学校やバレエ団にいるとき
みんな同じように大変な時期を過ごすんですよね。
試験、発表会、オーディション時期、舞台前…
愚痴を言い合ってスッキリする!という形なら良いのですが
お互いが同じように精神的なプレッシャーを消化できない場合
他の人からの愚痴が、自分の重りに感じる人はいます。
皆さんが、疲れている時は勉強ではなく
意味のない楽しいリールをずーっとスクロールするのと同じように
ストレス発散で現実逃避したい人も多い。
だから愚痴を言い続ける人の周りからは、人が減っていくと思います。
もしくは、同じように愚痴を言い合う人だけが残ります。
だって愚痴って一人じゃ出来ないからね。
残念ながら、この状況になると、普通の会話というか、デフォルトが愚痴なので
自分たちの中で愚痴を言っていることに気づかないという状況にもなってしまうようです。
ちょっと話がずれましたが、フィジカルヘルスはもちろんのこと
メンタルヘルスも一緒にケアするように意識が必要だというアドバイスでした。
そして健康を考えた場合、休憩を入れるのも大切ですが
必要な筋肉や体力を強化する必要があるのと同じように
メンタルヘルスを考えた場合、休憩も大切ですが
弱い部分は鍛えることを意識する必要があると思います。
芸術監督からのアドバイス その3:忍耐
デンマーク王立バレエ団芸術監督の最後のアドバイスは「忍耐強くあること」でした。
現代人はなんでもかんでも、すぐに結果を欲しがるけれど
バレエは時間がかかるという説明がありました。
何年もの間、コール・ド・バレエにいることがあっても
そこで学べることがある。チャンスが来るまで備えることが出来る。
だから焦らないで、というメッセージでした。
ネットにはたくさんの「コツ」が載っています。
- 足が上がるようになるコツ
- つま先を伸ばすコツ
- ストレッチのコツ
トウシューズで踊るコツなんていうのもありますよね。
これらすべて、正しいレッスンを歳月をかけて行うことが必要なんですが
それでは「いいね」が押される投稿にならないでしょう?
幼い時からのトウシューズも、なんでだか分からないけれど
学校がお休みのたびにコンクールに出場なども
周りの大人の忍耐不足なのかもしれません。
- 早く結果が出ないなら、受験すべき
- バレエ学校に入れないなら、踊りは辞めるべき
- 1回のオーディションで落ちたら、プロダンサーは諦めるべき
早く上達したいのはわかるけど、させたいのはわかるけど
間違った情報が結果として、変な癖につながったり、ケガにつながるし
周りの大人の焦りは、結果主義として子供たちのメンタルヘルスに影響します。
頭を使い、心身ともに健康なダンサーになろう
幼いころから、スポーツに特化してしまうと、つまり、バレエ一本にすると
バーンアウトなど精神的な問題が起こりやすいと言われています。
長くケガに苦しんでいたら、鬱になりやすいし
摂食障害は、食事の問題だけでなく精神病の1つです。
彼らがプロダンサーになりたかったら、なりたいほど
年齢にあったレッスンをすることや
健康と安全を最優先させることを徹底しなければいけません。
特に、どこでもかしこでも、トイレでも!
携帯で”ダンスインフルエンサー”の様子が見られるし
同い年の子たちがコンクール決戦で踊っている動画が流れてくることでしょう。
ダンスインフルエンサーというのは
カンパニーで踊ることがメインのお仕事なのではなく
ソーシャルメディアでの投稿や、スポンサーシップなどで
有名人のような仕事の人という意味ね。
悪いことではありませんよ。ただ、コロナで生まれた新しい職業の感じはありますよね。
ネットで有名ならチケットも出やすいでしょうから
新しい形の宣伝活動としてカンパニーがサポートしているとこともありますよね。
話をトイレの携帯に戻しましょう。
世界が指一本で見られちゃうもんだから
「それ (it)」が手に入っていない自分に焦りを感じる人も多いのかもしれません。
スクロール続きの早いペースでの情報に慣れてしまっているものだから
ゆっくり、忍耐強く待つことが出来ないのかもしれません。
親鳥が小鳥にご飯をのどに突っ込むように
アルゴリズムが情報を選択してくれちゃって、フィードにプッシュしてくるから
自分からリサーチしようと思わないのかもしれません。
目で見る情報が多いから
見た目だけにとらわれる考え方になってしまう可能性もあります。
だからこそ、バレエに関係している大人たち全員に伝えたい。
大人が焦るんじゃないよ。
そしてダンサーたちは、自分の頭を使い、会話力も磨いて
健康であることを第一に生活しましょう。
自分の夢なら、自分でリサーチして、正しい方向に努力しましょう。
思ったような結果にならなかった配役やケガは
ダンサーだったら避けられません。
だからこそ、周りに流されるのではなく、自分自身を強く持つ練習をしましょう。
機嫌の悪い先生や、常に愚痴っている仲間が周りにいる場合
自分を守る方法を学び、その環境が本当に自分を育ててくれるのか?を考えてみましょう。
DLSが、皆さんにとって
正しい情報を収集できて、勉強できる場所になっていますように。
ということで、海外バレエ団ディレクターから学ぶシリーズはここまで。
2025年最後となる来月のシリーズは「バレエ解剖学について」をお送りしていきます。
お楽しみに!
Happy Dancing!