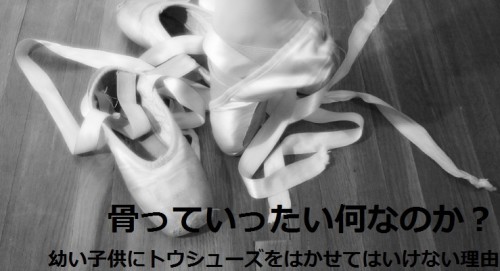バレエ学校で10年以上ダンサー向けの解剖学クラスを受け持っていた時も、2015年から20クラス以上行っている教師のためのバレエ解剖学講座でも、
最初に骨についてお話します。
なぜか?というと
- 骨の方が筋肉よりも数が少ない(=理解しやすい)
- アライメントやプレースメントなどレッスンですごく大事なところに直接影響する
- 疲労骨折や成長痛など、骨に影響するケガがダンサーにはよくある
から。
今日はダンサーにとって知っておくととっても便利な「骨」って何なのか?をお話しましょう。
骨クイズ!
まずは一緒にクイズをやってみましょうか。
〇×クイズ形式で答えてみてくださいね。
- Q1骨にも血管がある
- Q2赤ちゃんの方が大人よりも骨が多い
- Q3骨にも色々な形がある
- Q4男性と女性では骨の形が違う
- Q5骨の20−24%は水分でできている
どうでしたか?
正解は全てマルですが、全問正解しました?
なんでこの、どうでもいい骨クイズがバレエ解剖学につながるんでしょうか?
一つひとつを詳しく見てみましょう。
骨は生きている
骨は生きています。
化石みたいに、白い棒じゃなくって、中には血が通っています。
水分も入っています。
なのでダンサーに起こる怪我では骨折以外の骨の怪我も多く見られます。
疲労骨折はもちろん、ジャンプの着地で失敗すると骨を打撲することもありますし、骨膜炎になったりもします。
俗に言われる10代の「成長痛」(正式名称は成長期スポーツ障害)も骨のケガです。
それぞれのケガによって、そしてダンサーの生活によってケガの原因は違いますが、
骨を強くしたかったら(=骨量を増やしたかったら)食事をしなければいけません。
ただカルシウムのサプリメントを取っておけばいいのねーではなく、ダイエットせず十分にカロリーを取らないと骨量が増えません。
20代のピークを越えたら、骨量は落ちる一方ですが、ダンサーのプロ生活は始まったばかり。
不必要な疲労骨折などを防ぐためにも、骨は生きていて、食事をしないと栄養を送ることは出来ないんだ、ということを頭に入れておいてくださいね。
→この部分の詳細は疲労骨折の記事で説明しています。
食事、水分補給。
これは人間にとって「最低限必要な」行為であって、オプションではありません。
長く踊りたかったら、健康な人間であるという大前提から守らなければいけません。
当たり前だけど、発表会前になると痩せろって言ってくる先生がいるし、SNSも雑誌も専門家じゃない人たちが法的責任なしに好きなことを書いているので、ちゃんと理解してくださいね。
ダンサーにとって必要な食事について知りたい人は管理栄養士ふみさんのサイト、
英語の勉強も兼ねたいならば、元ダンサーで現ドクターのインスタアカウントフォローもお勧めします。
子供の方が骨の数が多いし、柔らかい
大人はだいたい206個骨があると言われますが人によって余分な骨があったり足りない人もいます。
私の生徒に2つの脊柱、つまり背骨がくっついていて1つになっている子がいましたし、教科書通りだと片足に2つあると言われる種子骨が4つくらいあった子もいました。
幼児の場合270個あたりの骨があるそうです。
そして年齢が上がるにつれてそれらの骨がくっついて私達大人の骨格になるわけ。
骨一つひとつ成長のスピードは違うし、ダンサーの成長も個人差がありますよね?
ほら、身長が高くなるスピードが違うように。
身長が伸びる=骨が伸びるだからね。
子供たちはまだ、骨が文字通り固まっていません。
こちらのサイトに0歳から5歳までの足のレントゲンがありました。
5歳でもまだ足の骨は完全にくっついていません。7歳ごろに足のアーチ(骨のアーチ)が出来るともいわれますし、足のサイズが大幅に変わるのは14-16歳くらいだけど、
完全に足の骨の成長が終わるのは18-20歳ごろです。

こちらのレントゲンは骨盤の成長という記事でご紹介していますが、3歳くらいの子供の骨盤だそうです。
骨盤を形成する3つの骨の塊はまだ離れているし、大腿骨の骨頭も骨化していないのが見えますよね?
早くからポワントを履かせてはいけない理由
ということで、子供たちの足はまだ完全にできていませんし、骨盤も1つの骨の塊になっていないということが分かってもらえましたか?
だからバレエ教師は
- 年齢に合わせてレッスン内容を考えなければいけないんです。
- 小さいうちに完璧な1番ポジションや5番ポジションはやりません。
- 無理やりストレッチもしません。
「小さいうちにストレッチしないと体が硬くなる!」
なんていう人たちがバレエ界や新体操界にいますが、幼いころのストレッチの有無だけがその子の人生すべての柔軟性に影響するわけがありません。
確かに骨がくっついていない=柔らかいですよ?動く場所が多いんだもの。
まだ骨化していないので、若い骨は弾力があり、柔らかいです。
でも、それはストレッチのチャンス!ではなくケガのリスクが高いってことだからね。
同じく、小さいときにポワントは履きません。
まだ人間として普通の生活をするだけの体が出来ていないのに、つま先の先で全体重を支えるという動きが出来るわけないじゃないですか。
コンクールで本、来はバレエ団のプリンシパルが踊るように振付されたバリエーションを
(プロになっても、そのレベルまで上がっていないダンサーは舞台で披露することが出来ない動きを!)
体がまだ出来上がっていなくて、骨が固まっていない子供にさせようと思っている人は将来の事をもう一度考えてください。
- 大きくなってバレエ団にオーディションに行く時にトウシューズ歴が入団を左右すると思いますか?
ローザンヌなど国際コンクールに出場するのに、10歳の時の入賞は役に立つのでしょうか? - 本当に生徒の成長と安全を考えてのチョイスですか?それとも自分のスタジオ売名行為ですか?
生徒のご両親が早くポワントを履かせてほしい、と言ってきたら教師がしっかりと説明してあげないといけません。
ご両親からすれば、バレエをやったらトウシューズを履くのが当たり前!って思っているかもしれないので、「これが普通」という固定観念がある場合があるかもしれません。
教師はプロ、保護者は素人だからね。
その時に科学的根拠が必要だ!という場合は国際ダンス医科学会(IADMS)が出しているこちらの資料をどうぞ。
でもバレエ界が…なんて言ってくる場合はYAGPで言われていることも載せておきます。
安全に、効率的に上達するためのバレエ解剖学を学びたい指導者は、教師のためのバレエ解剖学講座を
自分の足ってすげーなー!と興味が出た人や、トウシューズについて学びたい人はダンサーの足セミナーをどうぞ。
男性と女性では骨の形が違う
骨クイズの話に戻ってきましょうか。
大人と子供では骨の数や形が違うというのが分かってもらえたら、(生物学的な)男性と女性でも骨の形が違うということも知っておきましょう。
代表が骨盤。
骨盤は3つの骨で出来ているおわん上の骨格ですが、子供を約9ヶ月間お腹で運んだり、出産する必要がある女性は骨盤がもっとおわんに近い形をしていて、
男性はハートに近い形をしています。

なんでそれが大事かって?
解剖学の参考書に書かれているイラスト(写真)はだいたい、成人男性の場合が多いので
骨の形が違うんだ、ということを具体的に頭に入れておくことで、男の子でも女の子でも指導しやすくなるはずです。
人種によっても骨格は少し違います。
頭蓋骨の形はもちろん、脛の骨と大腿骨の比例にいたるまで、色々なところで違いがあります。
かといって、日本人みんなが同じ骨格じゃない、というのも友達の身長やお父さんとお母さんの顔を見比べたらわかりますよね?
骨格は個性があります。
それで良いんです。OOさんみたいにならなくても、XX人みたいにならなくても、
貴方というユニークな骨格に問題はありません。
- バレエ向きな体
- 恵まれた体型
なんて言葉を発する指導者がいますが、動ける体があるだけでバレエ向きだし、国、文化、時代が変わればダンサーに求められる体型が変わることはバレエ史を見たらわかるはずです。
骨にも仕事があります。
骨の仕事ってナンだと思います?
もちろん、人間に骨がなければくらげみたいになってしまい、ダンスはもちろん、陸上で動くことも大変になってしまうのではないでしょうか?
(そんな人にあったことがないので良く分かりませんが・・・)
骨の仕事はカルシウムを始めとして色々なものが貯蔵すること。
つまりラクダのこぶ。
栄養不足、食事&エネルギー不足だと、体は骨から栄養をとって使うようになります(筋肉もそうやって使われちゃうけどね)。
だから、ケガのリスクが高くなるんです。
骨の仕事というよりは、「骨格」の仕事にはなってしまうけれど、
- 体を支える
- 体を守る
という仕事もあります。
肋骨の中に守られているのが肺と心臓。
骨盤の上に乗っかっているのが様々な内臓たち。
頭蓋骨の中には脳みそ。
背骨の骨にも神経が通る穴があって、私達が動くのを助けてくれています。
骨格についてもっと知りたい人はこちらのビデオシリーズで無料授業をしているから見てみてね!
どうですか?骨について理解が増えました?
次は「関節:動きの生まれるところ」についてみていきましょう!
Happy Dancing!
 、
、
、