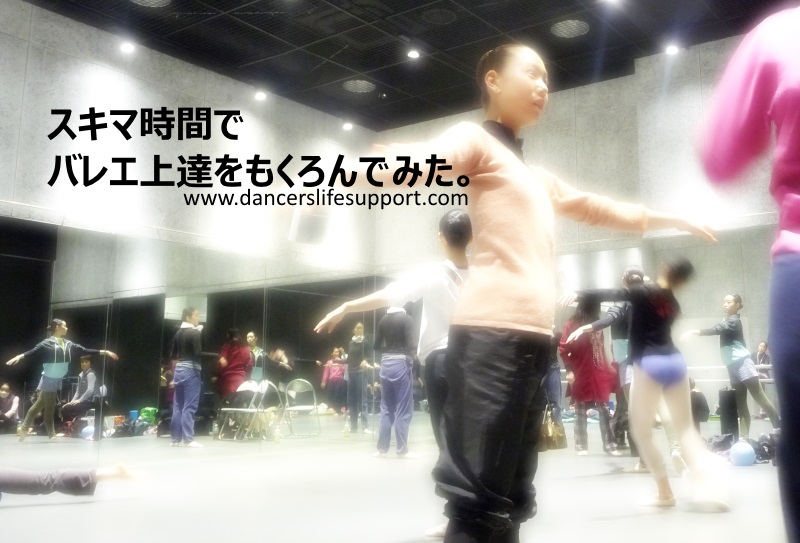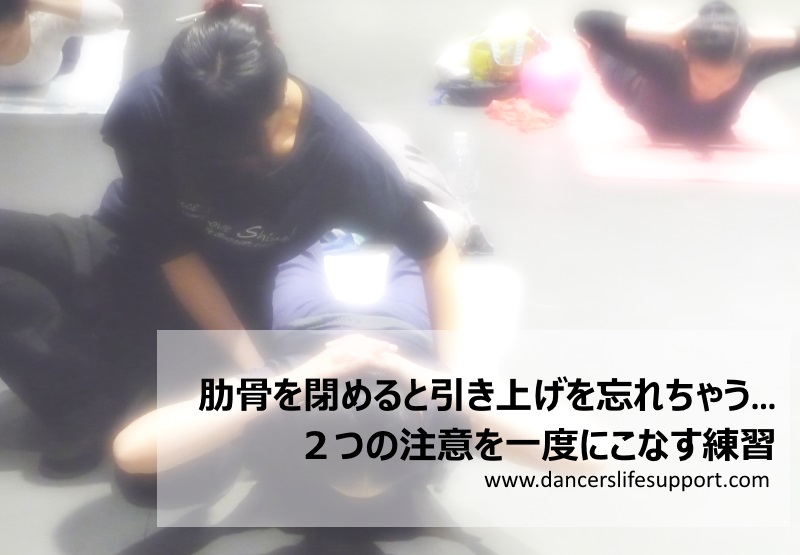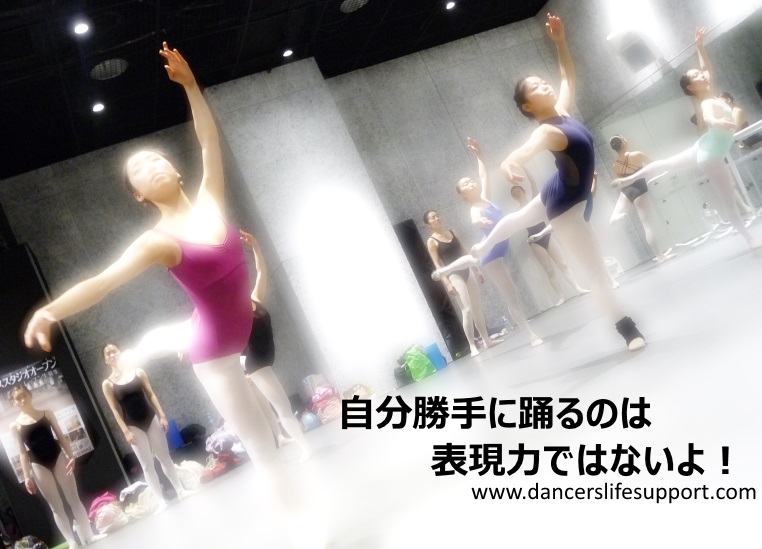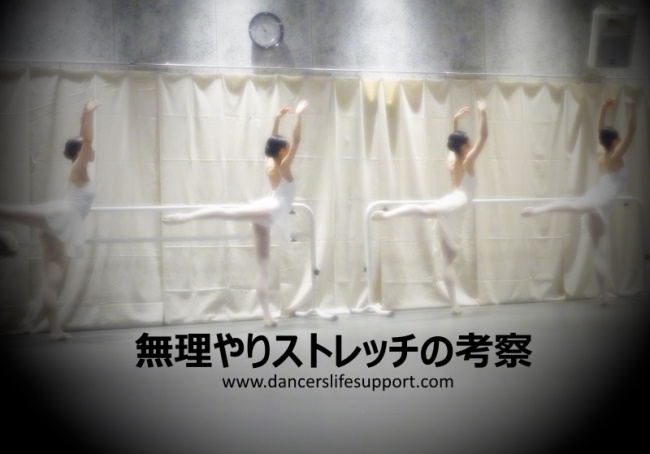治療家・トレーナーのためのセミナ― 2016年9月 赤裸々日記
9月来日最終日は治療家・トレーナーのセミナーでした。 嬉しいことに、前回4月に大阪で出会ったメンバーのほとんどが再度参加してくれたの。 これって素晴らしいと思いません? ダンサーをサポートしたいな、っていう方が定着していってくださっている証拠ですね。 今回は前半が「バレエの世界へようこそ」 ダンサーの世界って不思議なんですよ、ということを理解してもらうための内容でした。 もちろん、ダンサーの世界だけが不思議なんではありません。 オリンピック選手の世界。 歌舞伎など家業の世界。 宝塚の世界・・・ やっぱり不思議なものはたくさんあるのです。 それを知っていると、その世界にいる人達をサポートできる。 ということで、舞台の見方だったり、年齢的なもの、リハビリまで考えてもらいました。 今回はスペシャルゲストで、ケガしている若いダンサーに来てもらってありました。 様々な人に診てもらって、やっぱり痛みはよくならず、途方に暮れていた。 こんな話、ダンサーにはよくあります。 彼女を使って、ダンサーの言葉だったり、痛みだったりを研究していったの。 例えば「レッスン」という言葉と「練習」が指しているものの違い。 レッスンは普通のレッスンで、 練習は発表会だったり、コンクールだったりへの練習を指します。 そしてリハーサル、というとだいたい、全部を通すもので、一人ではリハと言う人は少ない、とかね。 そうすると彼女の生活が見えてくるってわけ。 そして痛みがあるのが生活なのか、踊りだけなのか?…