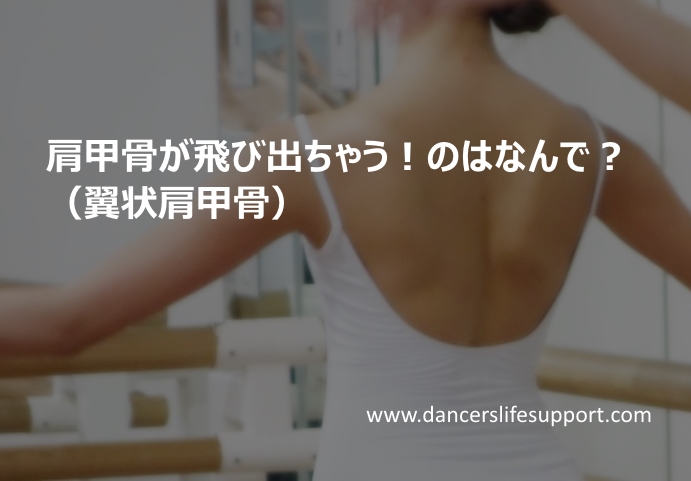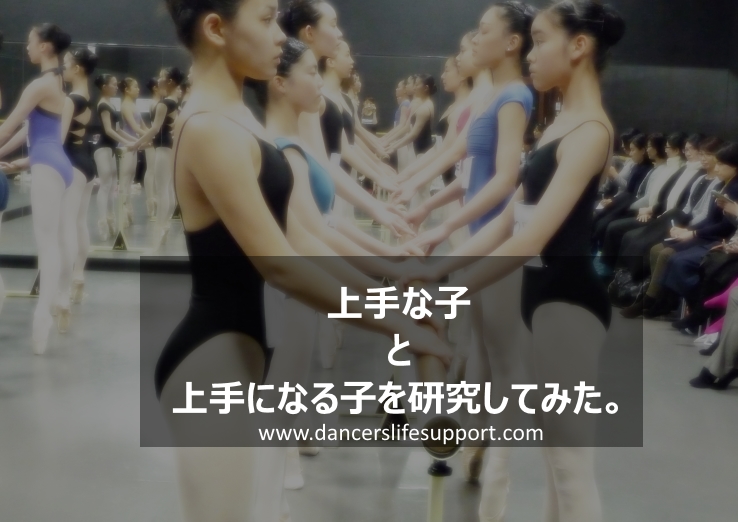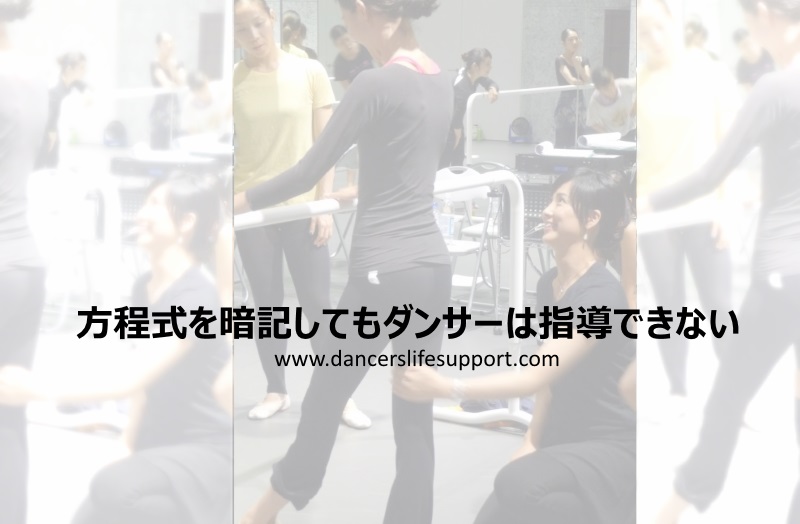肩甲骨のウイング修復エクササイズ(ダンサーの翼状肩甲骨)
今日のエクササイズはこの前の記事を読んでいなかったらほんとーにちんぷんかんぷんです。 (あ、なんだか平仮名の羅列になってしまった) なのでそっちをしっかりと読んでください。→肩甲骨が飛びだしちゃう!のはなんで? 形だけのエクササイズを真似していても、何をやっているのか理解できていなかたったら効果は殆どありません。 逆に、何をやっているのか明確に理解できて、自分でイメージしながらできたら上達が早まりますよ! さて、今日はウイングを直すためのエクササイズ。 自分で見えないエリアなのでさっき述べた理解とイメージがとっても大事です。 また、このエクササイズはしっかりと真っすぐにたつ!という事ができる人が行って下さい。 骨盤が安定しない、とか真っすぐに立てない・・・という子たちはそちらを先に練習すること。 まずは、ウイングのおさらい。 なんだかごっつく見える気がする、というのは放っておいて。 楽屋でとった写真なので、写真の角度が変なのと、このレオタードのカットが・・・なだけです。 見えないから片方ずつ行います。 同じ角度でウイングのことってほとんどないので、まずは少しよさめの方から(よさめって日本語か?)やってみましょう。 できる方で感覚をつかみ、その感覚をつかって難しいことをやる。 エクササイズ&ニューロンの基本ですね。 写真の様に手のひらを返して肩甲骨にふれます。 手や肩を動かしながら肩甲骨がうまくはまる場所を探しましょう。 ほとんどの人は肩を開き、持ちあげると肩甲骨がはまる場所が発見できるはずです。 それが分かったら、この位置をキープしたまま方を下げてきます。 途中で肩甲骨がいなくなっちゃったら、またもとに戻りましょう。 肩の上げ下げをしても、肩甲骨が静かに収まっている様になったら、その位置でポーデブラの練習をします。…